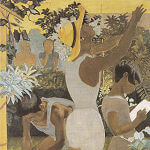大久保作次郎「舟遊図」
大久保作次郎(1890-1973)は、大阪市に生まれた。寺内萬治郎とは幼馴染。その後、上京して東京美術学校に進学し、黒田清輝、藤島武二に学んだ。同級に鍋井克之がいた。同校在学中の明治44年に第5回文展で初入選し、以後、官展(文展、帝展、日展)に出品を続けた。大正12年から昭和2年にかけては滞仏生活を送り、その間、ルーヴル美術館でボッティチェリを模写するなどした。
官展に出品を続けるかたわら、大正2年から大正8年まで光風会展に出品し、その後、滞仏中の大正13年に結成された槐樹社に参加、同社解散後は昭和15年に鈴木千久馬、中野和高、安宅安五郎らと創元会を結成したが2年後に退会した。戦後は、旺玄会に参加したが昭和29年に退会し、翌年、和田三造、川島理一郎、柚木久太、吉村芳松らと新世紀美術協会を結成した。
作風は、モダニズムの怒濤に揺れる当時の画壇のなかにあって、外光派ふうの穏健な表現を貫き、風景画のほか、屋外や窓辺に憩う人物を、時には逆光を効果的に使って生き生きと描写した。掲載の「舟遊図」は、マネやモネも好んだ優雅に舟遊びを楽しむ貴婦人の図で、庭の池に浮かべたボートでモデルにポーズを取らせて制作したという逸話が残っている。
大久保作次郎(1890-1973)おおくぼ・さくじろう
明治23年大阪市生まれ。旧姓は氏家。明治44年に叔父の大久保家を継いだ。東京美術学校在学中の明治44年第5回文展に初入選し、以後も出品を続け、大正5年から3年連続で特選となった。大正12年から昭和2年まで渡仏。この間に結成された槐樹社に参加した。帝展、新文展で審査員もつとめ、戦後は日展に出品した。昭和12年創元会の結成に参加。昭和30年新世紀美術協会の結成に参加。昭和34年日本芸術院賞を受賞。昭和38年日本芸術院会員となった。昭和48年、83歳で死去した。
大阪(142)-画人伝・INDEX
文献:日展100年、洋画家たちの青春、実力画家たちの忘れられていた日本洋画1