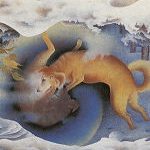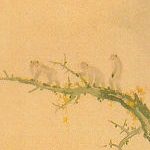望月金鳳「孔雀之図」
望月金鳳(1846-1915)は、大坂平野町に接骨医・平野浄恵の二男として生まれた。9歳の頃林仁鳳に円山派の手ほどきを受け「芳林」と号し、その後四条派の西山芳園・完瑛に学び「金鳳」と号した。17歳の時、剣道を以て立とうと養家を去り、京都地方の志士剣客と往来したが、時世の変遷で武術の道はあきらめ、明治9年上京して内務省につとめたのち、開拓使へと仕官した。
30歳の時に北海道に出張し、そのまま北海道庁の地理課の官吏として滞在した。その後の15年に及ぶ北海道での官吏としての暮らしのなかで、鶏、兎、孔雀、鶴だけでなく鷲や熊まで飼育し、狸は工夫して自宅で育てるなど動物の生態を研究し写生につとめた。
明治15年内国絵画共進会に北海道から作品を送り、明治23年職を辞して上京、第3回内国勧業博覧会にも出品し、浅草松清町に私塾を開いた。その後も主に日本美術協会に動物画を出品して金・銀・銅賞を受賞した。
明治29年に日本絵画協会が結成されると第3部に出品して1等褒状となったが、明治31年には日本絵画協会の審査の方針に不満を抱いた鈴木華邨らとともに日本画会を創設し、その審査員となった。新機軸という言葉を嫌い、つたなくても自分で研究した自分の絵を描けと門下を指導したという。
望月金鳳(1846-1915)もちづき・きんぽう
弘化3年大坂平野町生まれ。幼名は数馬。望月家を継いだ。別号に小蟹がある。9歳の頃に円山派の手ほどきを受け、四条派の西山芳園・完瑛にも学んだ。明治9年上京して内務省につとめ、その後北海道庁の官吏となった。独学で動物画の研究を深め第1回内国絵画共進会に出品。明治23年上京して画家として活動し、主に日本美術協会で受賞を重ね、明治31年日本画会を創設した。明治42年第2回文展で審査員をつとめた。正派同志会会員で再々宮内省の御用品となった。大正4年、69歳で死去した。
大阪(97)-画人伝・INDEX
文献:日本美術院百年史1巻上、近代の日本画