-

-
動物の生態を研究し写生につとめた望月金鳳
2025/4/7
望月金鳳「孔雀之図」 望月金鳳(1846-1915)は、大坂平野町に接骨医・平野浄恵の二男として生まれた。9歳の頃林仁鳳に円山派の手ほどきを受け「芳林」と号し、その後四条派の西山芳園・完瑛に学び「金鳳 ...
-

-
古き浪速の名勝地を描き人気を博した久保田桃水
2025/4/4
久保田桃水「大阪風景画帖」 久保田桃水(1841-1911)は、京都に生まれ、四条派の横山清暉に学び、清暉没後は19歳で大阪に移り西山芳園に師事した。明治20年に上京し皇居千種間の欄間や芝離宮洋館の天 ...
-

-
西山完瑛に学んだ武部秋畦・白鳳兄弟
2025/4/2
武部白鳳「雨樹栖鷲図」 武部秋畦(1868-1906)、武部白鳳(1871-1927)の兄弟は、歌川派の浮世絵師の流れを汲む画家・武部芳峰の子として大阪に生まれ、兄弟で西山完瑛(参考)の門に学んだ。兄 ...
-

-
船場派を率いる先達の役割を果たした西山完瑛
2025/3/31
西山完瑛「鸚鵡図」 西山完瑛(1834-1897)は、四条派の西山芳園の子として江戸後期の大坂に生まれた。父の芳園は、大坂に四条派を流行らせたとされる画家で、完瑛もその伝統を受け継ぎ、温雅で洒脱な人物 ...
-

-
平井直水、大塚春嶺ら深田直城の門人
2025/3/28
平井直水「梅花孔雀図」 平井直水(1860-不明)は、30歳で画家を志し深田直城に師事した。孔雀を描くのを得意とし、日本絵画協会などで受賞を重ね、明治40年に日本初の官展として開設された文展の第1回展 ...
-
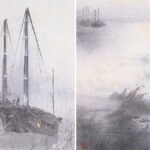
-
大阪四条派の重鎮として後進を育成した深田直城
2025/3/26
深田直城「水辺芦雁・雪中舩泊」 深田直城(1861-1947)は、近江国の膳所藩士の家に生まれた。8歳の時に京都に出て絵画を習いはじめ、14歳で父の友人である加島菱洲に洋画を学び、翌年森川曽文に師事し ...
-

-
終生「船場の絵描き」として生きた庭山耕園
2025/3/24
庭山耕園「舞楽図」 庭山耕園(1869-1942)は、現在の兵庫県姫路市に生まれた。庭山家は代々姫路藩の酒井家に仕えており、父は大坂の蔵屋敷の仕事に携わっていたが、明治初年の廃藩で職を失ったため家族で ...
-

-
写生的な作風で「精細麗艶」といわれた上田耕冲
2025/3/21
上田耕冲「箕面山真景図」逸翁美術館蔵 上田耕冲(1819-1911)は、円山応挙門下の上田耕夫の子として京都に生まれた。父に画を学び、父とともに大坂に移ったが、その後死別したため豪商・平野屋五兵衛の援 ...
-

-
大坂における四条派隆盛の基盤を築いた西山芳園
2024/9/27
西山芳園「龍安寺雪中図」黒川古文化研究所蔵 西山芳園(1804-1867)は、本町辺りの木綿問屋に生まれ、幼い頃つとめていた奉公先で画を描くことを勧められ、大坂琳派の中村芳中に師事した。師の「芳」の一 ...
-
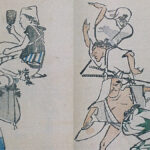
-
写生を本領とし『公長画譜』を出版した上田公長
2024/9/23
上田公長『公長画譜』の一部 上田公長(1788-1850)は、大坂船場の木綿問屋6代目・阿波屋忠次郎の長男として生まれ、天保頃は南久太郎町に住み、嘉永頃は道修町で暮らした。『上田公長正伝』によると、中 ...
-

-
呉春に学んで一家を成した大坂長堀の佐藤魚大
2024/9/20
佐藤保大(二代魚大)「狐行列」 佐藤魚大(不明-不明)は大坂の人で、呉春に学んで一家を成し、山水人物を得意とした。子にはともに画人の保大と守大がおり、保大は父の号を継いで二代魚大となり、明治期にも活躍 ...
-
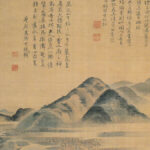
-
摂州池田の四条派・葛野宜春斎
2024/9/18
葛野宜春斎「呉里図」池田市立歴史民俗資料館蔵 葛野宜春斎(1771-1819)は、摂州池田(現在の大阪府池田市)の酒造業の家に生まれ、その頃池田に寓居していた呉春に師事した。呉春に学んだ期間は短かった ...
-

-
応挙と蕪村の折衷的な写生画を描いた上田耕夫
2024/9/16
上田耕夫「山水図」関西大学図書館蔵 上田耕夫(1759-1831or1832)は、摂州池田の人で長く京都に住み、文政後半頃に家族とともに大坂に引っ越したと思われる。京都に出たのは叔父の大徳寺無学和尚に ...
-
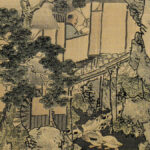
-
呉春から軽妙な写生画を受け継いだ長山孔寅
2024/9/13
長山孔寅「山水図」 近世大坂画壇で森派の森徹山と同時期に活躍した写生派の画家としては、四条派の長山孔寅がいる。孔寅は秋田の人で、京都に出て呉春に画を学びその後大坂に移った。田能村竹田にその写実性を賞賛 ...
-

-
播州龍野の円山派・山村翠谷
2023/12/25
山村翠谷「薔薇に錦鶏図」 外内松意ら龍野藩につかえた狩野派の絵師に対し、山村翠谷(1787-1850)は、若いころに京都に遊び、円山派を学んだ。一説には応挙門下十哲のひとり・奥文鳴に師事したという。家 ...
-

-
明治・大正期の京都画壇の重鎮として活躍した山元春挙
2024/12/13
山元春挙「しぐれ来る瀞峡」滋賀県立美術館蔵 旧膳所城下(滋賀県大津市)に生まれた山元春挙(1871-1933)は、小学校卒業後、大島一雄に漢詩文を学び、12歳の時に近江出身で四条派の野村文挙に師事して ...