-

-
動物の生態を研究し写生につとめた望月金鳳
2025/4/7
望月金鳳「孔雀之図」 望月金鳳(1846-1915)は、大坂平野町に接骨医・平野浄恵の二男として生まれた。9歳の頃林仁鳳に円山派の手ほどきを受け「芳林」と号し、その後四条派の西山芳園・完瑛に学び「金鳳 ...
-

-
船場派を率いる先達の役割を果たした西山完瑛
2025/3/31
西山完瑛「鸚鵡図」 西山完瑛(1834-1897)は、四条派の西山芳園の子として江戸後期の大坂に生まれた。父の芳園は、大坂に四条派を流行らせたとされる画家で、完瑛もその伝統を受け継ぎ、温雅で洒脱な人物 ...
-
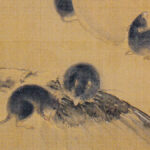
-
中井藍江に学び写生にも力を注いだ林文波
2024/12/6
林文波 左:「炭取鼠図」右:「百福の図」 林文波(1786-1845)は、はじめ蔀関月に師事し、その後、関月の門人である中井藍江に学んだ。山水花鳥を得意とし、また写生にも力を注ぎ、与謝蕪村を敬愛したと ...
-

-
黒田清輝らがもたらした外光派の影響を受け平明な風景画や静物画を描いた中村勝治郎
2024/7/7
中村勝治郎「静物」 中村勝治郎(1866-1922)は、現在の奈良市に生まれ、京都で山内愚仙に洋画を学んだ。その後、明治26年にフランス留学から帰国したばかりの黒田清輝と久米桂一郎と知り合い、教えを受 ...
-

-
興福院や円照寺に襖絵が残っている渡辺始興
2024/6/5
渡辺始興「農夫図屏風」東京国立博物館 渡辺始興(1683-1755)は、尾形光琳に学んだ光琳派の画家として知られるが、絵巻の研究によって大和絵系の筆法も学び、狩野尚信を慕って狩野派の骨法にも習熟し、晩 ...
-
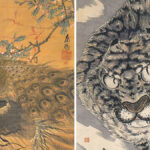
-
江戸で殺人を犯し逃亡先の長崎で画を学んだ島琴陵
2024/1/22
島琴陵「海棠孔雀図」 島琴陵(1782-1862)の前半生はよく分かっていないが、もと南部藩士で、江戸で人を殺して出奔し、逃亡先の長崎で来舶清人らと交遊して画を学んだと伝わっている。長崎派の写実的な花 ...
-

-
市川其融ら鈴木其一の流れを汲む画人
2024/1/17
市川其融「四季草花虫図」 酒井抱一の実質的な後継者となった鈴木其一は、抱一没後に自ら願い出て酒井家に一代絵師として仕えた。しかし、表向きは酒井家の御用絵師だったが、パトロンを得ることも認められていたよ ...
-

-
源氏流いけばなを創始し一世を風靡した千葉龍卜
2023/12/29
千葉龍卜「牡丹に猫図」神戸市立博物館蔵 千葉龍卜(不明-1800or1808)は、播州赤穂有年原(現在の赤穂市有年原)の明源寺に生まれた。華道を本業とし、京都・大坂を経て江戸に出て「源氏流いけばな」を ...
-

-
桜画を専門に描いた三熊派の祖・三熊花顛
2023/3/27
三熊花顛「八重山桜図」六如慈周賛 江戸時代中期の京都において、桜の絵を専門に描く画家たちがいた。その始祖は、『近世畸人伝』の発案者として知られる三熊花顛(1730-1794)で、花顛は、桜の品種や銘木 ...
-

-
独学で洋画を描き28歳で没した手塚一夫
2021/7/25
手塚一夫「村娘」 手塚一夫(1911-1939)は、山梨県中巨摩郡百田村(現在の南アルプス市)の養蚕農家の長男として生まれた。小学生の頃から図画が好きで、紙がないときには運動場の地面に絵を描いていた。 ...
-

-
山梨県内の洋画黎明期の画家
2021/7/5
土屋義郎「机上のざくろ」山梨県立美術館蔵 山梨県出身の洋画家としては、明治初期に活躍した中丸精十郎をはじめ、女性初の二科会友となった埴原久和代や渡仏して学んだ石原長光らがいるが、山梨県内で洋画団体が結 ...
-

-
独立展の重鎮の一人として活躍した中村節也
2021/7/5
中村節也「静物」群馬県立近代美術館蔵 中村節也(1905-1991)は、群馬県邑楽郡長柄村(現在の邑楽郡邑楽町)に生まれた。父親は郡役所の官吏だったが、大正11年に銀行員に転職、それに伴い中村も高崎市 ...
-

-
東京美術学校在学中に渡仏し12年間滞在した南城一夫
2021/7/5
南城一夫「鯛の静物」群馬県立近代美術館蔵 前橋に生まれた南城一夫(1900-1986)は、群馬師範学校附属小学校を卒業後、旧制前橋中学校に入学、同期には洋画家の横堀角次郎、詩人の萩原恭次郎、先輩には後 ...
-

-
欧州からの帰国後に東光会を創立、多くの後進を育成した熊岡美彦
2024/12/11
熊岡美彦「花」茨城県近代美術館蔵 熊岡美彦(1889-1944)は、茨城県の石岡に生まれた。生家は地元の素封家で、製糸業を営んでいた。石岡第一尋常小学校在学中は地元の南画家・鬼沢小蘭に学び、土浦中 ...
-

-
谷文晁門下四哲のひとり・立原杏所
2021/7/6
立原杏所 左:「蘆雁図」、右:「葡萄図」(重文) 立原杏所(1785-1840)は、水戸彰考館総裁・立原翠軒の長男として水戸下市横竹隈に生まれた。杏所の号は邸内にあった杏の木によったという。画をはじめ ...
-
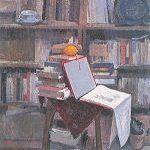
-
レモンの画家・小館善四郎
2021/7/6
小館善四郎「れもん」 青森市の裕福な木材商の四男として生まれた小館善四郎(1914-2003)は、小学生のころから油彩をはじめ、多くの芸術家を輩出した青森中学校に進んだ。同級生には、関野凖一郎、佐藤米 ...