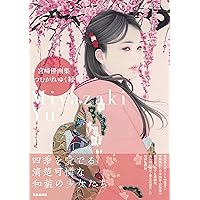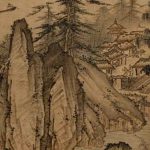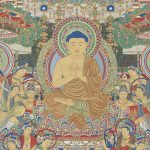秦致貞「聖徳太子絵伝」(10面のうち2面)国宝 東京国立博物館蔵
「聖徳太子絵伝」は聖徳太子の生涯と功績を絵画化したもので、その制作には、古代から天王寺がひとつの拠点として存在したことがわかっており、記録上では、すでに宝亀2年(771)に四天王寺絵堂に聖徳太子絵伝障子絵が存在したことが知られている。現存する最古の作例としては、延久元年(1069)に摂津国の絵師・秦致貞によって描かれた法隆寺東院絵殿の障子絵があり、現在は東京国立博物館に法隆寺献納宝物のひとつとして所蔵されている。
作者の秦致貞についての詳細は不明で、その姓から渡来系の一族であるとみられる。「聖徳太子絵伝」を描いた同じ年に、信貴山の僧・円快によって制作された絵殿に安置された聖徳太子坐像に彩色を施したことが知られるのみである。
ほかに、実作が残っていない平安期の主なやまと絵師としては、巨勢派の祖・巨勢金岡らがいる。金岡は平安初期に活躍した宮廷絵師で、やまと絵の祖ともされる存在で、巨勢派を通じてのちの日本絵画に大きな影響を及ぼした。仏画などに金岡の作に擬する伝承作品は多いが、確証のあるものはない。また、平安中期に宮廷絵師として活躍し、やまと絵の成立・発展に貢献した飛鳥部常則の名もよく知られているが、確証のある作品は残っていない。
平安後期の宮廷絵師・藤原隆能は、天皇の命により肖像画や寺院装飾など、多様な制作を行なったと推測されるが実作は残っていない。「源氏物語絵巻」の作者との伝承もあるが不明で、確証はない。
秦致貞(不明-不明)はた・の・ちめい
平安中期の絵師。渡来系氏族である秦氏の一族とみられる。延久元年法隆寺絵殿の内部壁画の障子(襖)に「聖徳太子絵伝」を描いた。また同じ年に造られた聖徳太子坐像の彩色をしたことも、同像の胎内銘からわかる。
巨勢金岡(不明-不明)こせ・の・かなおか
平安初期の宮廷絵師。唐様式が主流だった時代に、やまと絵の基礎を築いたといわれる。大学寮に孔子とその門人の像を描き、一方で御所の障子(襖)には詩作にすぐれた日本の儒者の像を描いたことが伝えられている。仁和元年には太政大臣藤原基経の50歳の賀の屏風を描いたという。実作は残っていないが、宮廷の障壁画制作や自然を写実的に描いた功績が伝えられる。
飛鳥部常則(不明-不明)あすかべ・の・つねのり
平安中期の宮廷絵師。やまと絵の成立・発展に貢献した。藤原行成の日記『権記』によると藤原道長の長女彰子の入内のために用意した「倭絵」屏風に描いており、文献上「やまと絵」の語が登場する初例である。
藤原隆能(不明-不明)ふじわら・の・たかよし
平安後期の宮廷絵師。仁平4年鳥羽金剛心院の扉絵を描き、後白河法皇の命で鳥羽上皇の肖像を描いたとされる。また、久安3年に藤原忠実の70歳の賀に因む蒔絵硯箱の絵様を描いたという。「源氏物語絵巻」の作者との伝承もあるが不明で、確証のある作品はない。
京都(04)-画人伝・INDEX
文献:本朝画史、もっと知りたいやまと絵、やまと絵 日本絵画の原点