-

-
播州赤穂の近代画人・長安義信
2023/12/27
長安義信「文王呂尚図」 長安義信(1788-1868)は、幼少のころ大坂で土佐派の画人・佐野龍雲について画を学んだ。40歳の時に法橋に叙され、赤穂に戻って花岳寺の門前に住んだ。土佐派以外にも狩野派、写 ...
-

-
大和絵新興運動を興し大和絵に近代的な感覚を取り入れた岩田正巳
2022/6/1
岩田正巳「写真」 岩田正巳(1893-1983)は、新潟県南蒲原郡裏館村(現在の三条市)に眼科医の長男として生まれた。教養人だった父は、医業のかたわら漢詩をたしなみ、愛山と号して水墨画を描いていた。正 ...
-
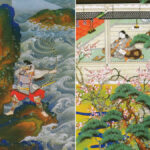
-
退色しにくい「津端式絵具」を開発した津端道彦
2022/4/22
津端道彦「文武」 津端道彦(1868-1938)は、新潟県中魚沼郡外丸村(現在の津南町外丸本村)に生まれた。生家は酒造業を営んでおり「菊水」という銘柄の酒を造っていた。父の荘六は藍亭と号して南画を描い ...
-

-
松本に多くの作品を残した勤皇画人・浮田一蕙
2021/9/6
浮田一蕙「婚怪草紙」(部分) 松本地方の近代日本画の発展には、県外から来た2人の勤皇画人も重要な役割を果たした。ひとりは、2度にわたり京都から訪れた復古大和絵の浮田一蕙で、もうひとりは、伯耆国(鳥取県 ...
-

-
近代歴史画の父・小堀鞆音
2024/12/11
小堀鞆音「恩賜の御衣」栃木県立美術館蔵 現在の佐野市に生まれた小堀鞆音(1864-1931)は、20歳頃に上京、土佐派の川崎千虎について歴史画を学んだ。明治25年には岡倉天心を会頭とする日本青年絵画協 ...
-

-
日光山の絵事に携わったやまと絵住吉派二代・住吉具慶
2021/7/6
住吉具慶「洛中洛外図巻」(部分)東京国立博物館蔵提供:東京国立博物館研究情報アーカイブズ 日光東照宮の絵画御用には、狩野探幽、神田宗庭、木村了琢のほか、やまと絵住吉派の住吉具慶(1631-1705)も ...
-

-
緻密な時代考証を加えた歴史画を手掛けた荻生天泉
2021/7/6
荻生天泉「小楠公」南北朝時代、南朝側の武士だった楠木正行が、死を覚悟して北朝軍との戦いに向かう際、後醍醐天皇廟の前の如意輪堂の壁に、矢尻で「辞世の句」を刻む姿を描いている。 福島県安達郡太田村荻ノ田( ...
-
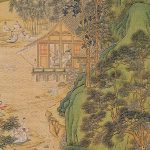
-
復古大和絵を学び、のちに谷文晁門下の高久靄厓の後を継ぎ、大和絵と南画を融合した画風を確立した高久隆古
2021/7/6
高久隆古「蘭亭曲水図」栃木県立博物館蔵 高久隆古〔高隆古〕(1810-1858)は、文化7年に忍城下(現在の埼玉県行田市)に阿部家の家臣・川勝隆任の子として生まれた。阿部家は三河以来の徳川家譜代大名と ...
-
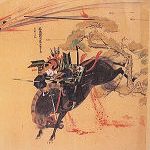
-
肥後土佐派の祖・福田太華
2021/7/6
福田太華「蒙古襲来絵詞模本」菊池神社本 熊本における復古大和絵の展開は、文政11年に福田太華(1796-1854)が《蒙古襲来絵詞》の模写を始めたことが始まりとされる。太華は専門の絵師ではなく、熊本藩 ...
-

-
福岡藩御用絵師・衣笠家と上田家
2021/7/6
衣笠守昌「牛馬図屏風」(部分) 福岡藩御用絵師筆頭の尾形家が、藩主画像や城郭殿舎の内部絵付、席画や寺社の寄進画の制作などを主な仕事にしていたのに比べ、次席に位置する衣笠家が藩主画像や席画の御用にあたっ ...
-

-
福山藩の住吉派・村片相覧と藩主・阿部正精
2021/7/9
村片相覧「高士幽棲図」 福山藩主の阿部氏は代々、学問、文芸、芸術などを積極的に奨励し、藩主自らも風雅を好み、画を描いた。なかでも三代阿部正右(1724-1769)、四代阿部正倫(1745-1805)、 ...
-
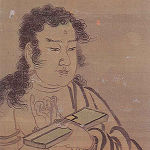
-
土佐派の流れを汲む画僧・鶴洲と讃岐の土佐派
2022/9/3
鶴洲「文殊菩薩図」 讃岐において、狩野派の画僧・實山と並び称されるのが、土佐派の流れを汲む画僧・鶴洲である。後年の活動から鶴洲を土佐派の画人とするには異論もあるが、鶴洲は、住吉派の祖である住吉如慶の子 ...
-
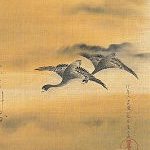
-
伊予松山藩の住吉派絵師、遠藤広古・広実
2021/7/9
遠藤広古「月に雁図」 江戸の狩野派は武家社会に受け入れられ、日本各地で絶大な勢力を誇った。伊予松山藩においても、初代の松本山雪から明治にいたるまで、代々狩野派が御用絵師を引き継いでいたが、その途中で、 ...
-

-
土佐唯一の土佐派・滝口国成と諸派の画人
2021/7/9
滝口国成「衣川の戦双幅」 近世の土佐では、藩の御用絵師は狩野派がつとめ、知識人の間では南画が広まっていた。そのためか、その他の流派はきわめて少ない。記録にある画人としては、土佐光貞に学んだ滝口国成(不 ...
-

-
近代徳島の住吉派、森魚渕・多田藍香・湯浅桑月と門人たち
2022/8/20
森魚渕「藤原公任之図」 阿波の住吉派の第一人者である守住貫魚の門下で最も傑出した画人と称された森魚渕(1830-1909)は、ほとんどを徳島の地で活動し、地元画壇の発展に貢献した。明治20年代にできた ...
-

-
阿波の住吉派の第一人者・守住貫魚と門人
2022/8/20
守住貫魚「騎馬武者像」徳島市立徳島城博物館蔵 守住貫魚(1809-1892)は、同郷の渡辺広輝に学んだのち、住吉広定に師事、住吉派の御用絵師として阿波蜂須賀家に仕えた。また、江戸時代に火がついた歴史ブ ...