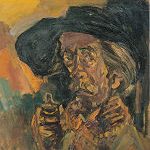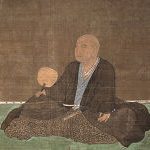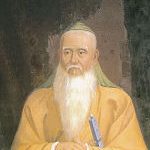左:伝藤原隆信「伝源頼朝(足利直義)像」京都・神護寺蔵
右:伝藤原信実「柿本人麻呂像」東京国立博物館蔵
「似絵」(にせえ)は、平安後期に確立された写実的で記録性の高い肖像画の様式で、「像主に似せた絵」とう意味で用いられることが多い。それ以前の肖像画は、あからさまな表現を避けた理想的・類型的なものだったが、「似絵」はそんな従来の表現から離れ、個性や人柄をとらえた写実的な描写を目指した。
歌人としても知られる藤原隆信(1142-1205)が祖とされ、その子・信実が技法を受け継いで大成させた。その後「似絵」は、隆信・信実の家系の家芸として、およそ7世180年にわたって継承され、主に宮廷や貴族社会での公的肖像画、特に歌人や有力貴族の姿を記録するために制作された。
広く知られている「伝源頼朝(足利直義)像」(掲載作品)は、長年、隆信の筆による源頼朝像と考えられてきたが、作者は、制作年代から隆信本人ではなく、信実あるいは工房の継承絵師によるものとする説がある。また、モデルについても、近年、貞和1年(1345)に足利直義によって書かれた願文が発見され、兄・尊氏と自らの画像を神護寺に奉納したと記されていることから、本図を直義像とする新説が出ている。
藤原隆信(1142-1205)ふじわら・の・たかのぶ
康治元年京都生まれ。藤原北家の流れを汲む一族で、藤原為信の子。藤原信実の父。藤原定家は異父弟にあたる。宮廷画家として公式の絵画制作を担い、写実的で記録性の高い肖像画の様式「似絵」を確立した。元久2年、64歳で死去した。
藤原信実(1176?-1265?)ふじわら・の・のぶざね
安元2年頃生まれ。宮廷画家、歌人。藤原隆信の子。初名は隆実。中務権大輔を経て、正四位下・左京権大夫となった。父隆信の技法を受け継いで「似絵」を大成させた。晩年に出家して「寂西」を名乗った。宮廷歌人としても活躍し、歌集『信実朝臣集』や説話集『今物語』の編者としても知られる。
京都(02)-画人伝・INDEX
文献:本朝画史、日本絵画名作101選、もっと知りたいやまと絵、やまと絵 日本絵画の原点