-
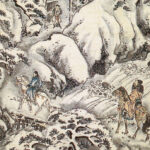
-
四条派の師風を守った関長年
2021/9/17
信濃国下高井郡松川村(現在の中野市松川)の豪商の家に生まれた関長年(1813-1877)は、20歳の時に江戸に出て四条派の大西椿年に師事し、師の一字をもらい「長年」と号した。26歳頃には長崎に出かけ、 ...
-

-
木曽の近世画人・馬籠宿の蜂谷蘭洲
2021/9/17
蜂谷蘭洲(1756-1840)は、信濃国木曽郡神坂村馬籠(現在は岐阜県中津川市)に生まれた。幼いころから画が好きで、青年になって伊勢山田の画僧・月僊について学んだ。山水や人物を得意とし、門弟のなかでも ...
-

-
晩年は世相を風刺した妖怪画を多く描いた高井鴻山
2021/9/13
高井鴻山(1806-1883)は、上高井郡小布施村(現在の小布施町)に生まれた。生家は江戸初期以来の旧家で、商業を営み、京都九条家及び諸藩の御用達をつとめていた。鴻山は15歳の時に京都に遊学し、摩島松 ...
-
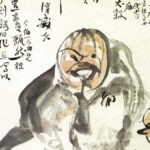
-
古曳盤谷門下の三筆、藤森桂谷・窪田松門・丸山素屋
2025/2/26
古曳盤谷は松本の飯田町に寄寓し、医業のかたわら南画や漢詩文の家塾を開き、多くの門人を育てた。主な門人としては、啓蒙運動家として活動し、国民教育の先覚者でもあった藤森桂谷、自由民権家で「信飛新聞」の創刊 ...
-

-
中信地方に南画を本格的に紹介した古曳盤谷
2021/9/8
古曳盤谷(1807-1885)は、伯耆国会見郡榎大谷(現在の米子市榎原)に生まれた。父盤嶺は医者で儒者だったが、文武両道に秀でており、盤谷は父から医術、漢学のほか武術も学び、さらに幼いころから絵筆をと ...
-

-
松本に多くの作品を残した勤皇画人・浮田一蕙
2021/9/6
松本地方の近代日本画の発展には、県外から来た2人の勤皇画人も重要な役割を果たした。ひとりは、2度にわたり京都から訪れた復古大和絵の浮田一蕙で、もうひとりは、伯耆国(鳥取県)出身の医師で南画家の古曳盤谷 ...
-

-
松本における近代日本画の基礎を築いた仙石翠淵
2021/9/3
仙石翠淵(1801-1885)は、筑摩郡埴原村(現在の松本市中山)に生まれた。生家は、胡桃澤膏薬本舗として近郷に知られていた。幼いころから書画を好み、独学で画を学んだが、49歳の時に旅の絵師・碧鳳に本 ...
-
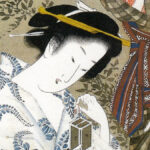
-
信州松本に流寓した江戸の人気浮世絵師・抱亭五清
2024/12/14
抱亭五清(不明-1835)は、葛飾北斎の門人で、北斎の下絵を描いていたとされる。当時、北斎門下の絵師たちは腕のたつものばかりだったが、そのなかでも際立った存在が抱亭だったという。抱亭は、狂歌作家を紹介 ...
-

-
飯山で児玉果亭ら多くの門人を育てた佐久間雲窓
2021/8/31
佐久間雲窓(1801-1884)は、飯山藩士の家に生まれ、その後、藩の吟味役をつとめた。幼いころから画を好み、30歳頃、藩主の参勤交代に随行して江戸に上り、許可を得て谷文晁門下の鏑木雲潭に師事し、雲潭 ...
-
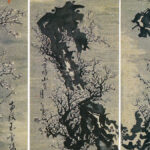
-
上尾に私立聖堂を建立した飯山の画僧・武田雲室
2021/8/30
武田雲室(1753-1827)は、飯山愛宕町の浄土真宗本願寺派三枝山光蓮寺で武田恵隋の長男として生まれた。光蓮寺は、武田信玄の弟・武田信繁の孫にあたる武田正善が開基したと伝えられている。 雲室は、11 ...
-

-
近世の信州を代表する画人・佐竹蓬平と鈴木芙蓉
2021/8/28
佐竹蓬平(1750-1807)と鈴木芙蓉(1749or1752-1816)は、ともに飯田の近郊・伊賀良の里に生まれ、年齢も近く(芙蓉の生年には2説ある)、ともに白隠慧鶴の高弟・寒山禅師が開いた寺小屋で ...
-

-
松代藩の閨秀画家・恩田緑蔭
2021/8/26
恩田緑蔭(1819-1874)は、松代藩で活動した女性画家で、松代藩士・四代恩田織部(恩田民正)の長女として生まれた。恩田織部の家は、代々二百石を継承する比較的裕福な家で、初代の恩田民格は、18世紀に ...
-

-
ペリー応接に同席し写生した松代藩医師・高川文筌
2021/8/25
嘉永6年(1853)、ペリー率いるアメリカ艦隊が浦賀に現れると、松代藩は品川に設けられた台場の警衛を担当し、翌7年のペリー再来航でも、横浜に設けられた応接場の警衛を小倉藩とともにつとめた。当時の松代藩 ...
-

-
松代藩御用絵師・大島芳暁斎と大島家三代
2021/8/23
三代にわたって松代藩の絵師をつとめた大島家の初代・大島芳雲斎(1766-1840)は、天明年間に江戸に出て木挽町狩野家に入門した。この時期は、松代藩江戸詰の絵師として木挽町狩野家の門人だった晩年の三村 ...
-

-
松代藩御用絵師・三村晴山
2021/8/20
松代藩に任えた絵師として記録上最も早く登場するのは、三村自閑斎(不明-不明)である。自閑斎は、一郎平と名乗り、藩評定所の絵図書をつとめていたとされ、現在残る作品も絵図に類するものである。師系は不明だが ...
-

-
信州小県郡で「田舎探幽」と呼ばれた秦燕恪
2021/8/18
秦燕恪(1732-1799)は、小県郡和田村(現在の小県郡長和町)に生まれ、はじめは狩野玉燕の作風を慕って私淑したが、のちに江戸に出て木挽町狩野家六代目の狩野栄川院典信の門に入った。その後帰郷して地元 ...