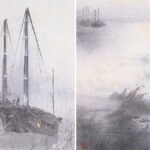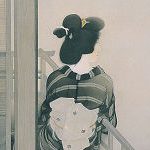北野恒富「鏡の前」
明治36年、大阪で第5回内国勧業博覧会が開催されると、多数展示された東京の画家たちの作品に刺激され、大阪の画家たちの間でも新しい表現を求める活動が盛んになっていった。その中心的な役割を果たしたのが北野恒富(参考)で、のちに恒富とその門人たちが手掛ける人物画は、「大阪の人物画」として花開いていった。
北野恒富(1880-1947)は、現在の石川県金沢市に生まれ、明治30年に大阪に出て、同じ金沢出身の稲野年恒に師事し、新聞小説の挿絵画家として人気を博した。そのかたわら様々な画系の作風を独習し、明治43年に第4回文展に初入選を果たし、その翌年の文展では3等賞を受賞し、全国的にその名を知られるようになった。
恒富の描く女性像は、従来の典型的な美女を描いた美人画とは異なり、人物の内面に迫ろうとするもので、その妖艶で退廃的な雰囲気から、一時期は「画壇の悪魔派」とも称された。その後も恒富は、移り行く時代にあわせて、描き方や人物表現を変えながら新たな境地を開拓し、晩年は清澄で洒脱なものへと変化していった。
恒富は、大正美術会、大阪美術展覧会、大阪茶話会などの設立に関与し、大阪の日本画界の振興に貢献するとともに、画塾「白耀社」を主宰し、島成園(参考)、木谷千種(参考)ら多くの女性画家を育成し、大阪画壇における女性画家の活躍に尽力した。
北野恒富(1880-1947)きたの・つねとみ
→妖艶で頽廃美漂う画風を展開し、画壇の悪魔派と呼ばれた北野恒富
大阪(118)-画人伝・INDEX
文献:サロン!雅と俗:京の大家と知られざる大坂画壇、日本美術院百年史3巻上、同4巻、大阪の日本画、上島鳳山と大阪の画家たち、大阪ゆかりの日本画家、大坂画壇の絵画、麗しき女性の美、美人画の系譜、近代日本画にみる麗しき女性たち