-

-
日本初の株式会社の設立を画策して毒殺された北斎門下の洋学者・本間北曜
2021/7/6
酒田の本間家分家に生まれた本間北曜は、天保13年、出羽矢島藩の小番郡八の養子となり藩主に従って江戸へ上るが、翌年出奔して離縁になった。この頃、小石川巣鴨の根付師・山口友親(初代竹陽斎)ついて彫刻を学び ...
-

-
葛飾北斎に学んだ庄内藩士・大山北李
2021/7/6
庄内出身の浮世絵師としては、葛飾北斎に学んだ庄内藩士・大山北李がいる。北李は、鶴崎に生まれ、文化4年家督を継いで江戸定府を命じられ、江戸神田松枝町に住んだという。その間、北斎に師事し浮世絵師として名を ...
-

-
やまと絵や琳派のスタイルも取り入れた狩野了承
2021/7/6
江戸幕府の御用絵師としての地位を得て、巨大な組織をつくりあげていった江戸狩野派は、やがて粉本主義に陥り、創造性を失っていったとされる。しかし、その歴史のなかで、江戸狩野派は幾度かの変貌を遂げ、絵師のな ...
-

-
庄内藩の御用絵師・三村常和
2021/7/6
元和8年、酒井忠勝が信州松代から庄内に入部し、鶴ケ岡城を居城と定められて以来、城内は着々と整備されていったが、本丸の建物が完成するのは30年後の承応2年のことだった。ちょうどこの年、前々年の慶安4年に ...
-

-
明治大正期、日本画壇旧派の重鎮として政治的手腕を発揮した下條桂谷
2021/7/6
米沢に生まれた下條桂谷は、はじめ郷里で目賀多家で狩野派の画法を学び、のちに江戸に出て鍛冶橋狩野家の門に入ったとされる。明治8年には狩野探美らと古書画鑑賞会を興し、明治12年に龍池会の結成に参加した。 ...
-
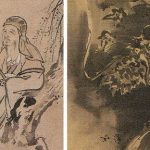
-
目賀多家に学んだ米沢の絵師たち
2021/7/6
米沢では絵を学ぶ者の大半が目賀多家に入門したことから、狩野派の画風が主流で、主な絵師としては、目賀多雲川守息に学んだ小田切寒松軒をはじめ、目賀多雲川信済に学んだ若井牛山、百束幽谷らがおり、佐藤雪斎、中 ...
-

-
目賀多家で最も傑出した名人と伝えられる目賀多雲川信済
2021/7/6
文政・天保の頃、米沢藩御用絵師の家系・目賀多家の分家である南目賀多家から出た目賀多雲川信済は、南・北目賀多家を通じてもっとも傑出した名人と伝えられている。瘦せ肉の体格ながらも、豪放にして酒を愛し、雪舟 ...
-

-
目賀多雲川守息に学び人物花鳥の名手として名を馳せた小田切寒松軒
2021/7/6
江戸時代の米沢の絵画界は、藩御用絵師の目賀多家を中心に展開し、米沢藩士のなかには絵画の家系でなくとも絵を学んだものもいた。法泉寺の庭園を修復したことでも知られる小田切寒松軒は、幼くして目賀多雲川守息の ...
-
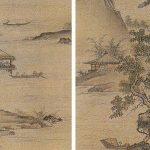
-
米沢藩の御用絵師・目賀多雲川守息
2021/7/6
米沢藩の御用絵師をつとめた目賀多家は、幕末にいたるまで代々江戸の鍛冶橋狩野家に入門して画技を習得し、狩野派の画風を継承した。目賀多家は二家あり、本家である幽雲系を北目賀多、分家である雲川 ...
-
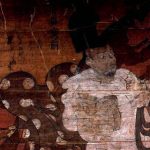
-
山形県で最も早く名前が登場する画人・郷目貞繁
2021/7/6
山形県の美術史上、最も早く画家として名前が登場するのは、室町時代末期に寒河江の大江家に仕えた武人・郷目貞繁(不明-不明)である。村山地方には、貞繁の作とされる絵画が20点ほど残っており、なかでも著名な ...
-

-
美術文化協会の結成に参加した浜松小源太
2021/7/6
秋田県大館市に生まれた浜松小源太(1911-1945)は、秋田師範学校専攻科を卒業後、地元の小学校につとめながら制作につとめ、昭和6年に開催された第1回独立美術展に入選した。その後は同郷の伊藤弥太の門 ...
-
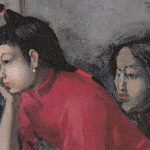
-
ブルースの女王・淡谷のり子を専属モデルにしたことでも知られる田口省吾
2021/7/6
田口省吾(1897-1943)は、明治30年東京文京区本郷に生まれた。父の田口掬汀は、秋田県角館出身の小説家で、美術雑誌「中央美術」を創刊し、美術評論も手掛けていた。省吾は、美術家や文化人らの出入りが ...
-

-
横手市の郷土史研究にも携わった金沢秀之助
2021/7/6
金沢秀之助(1894-1967)は横手市に生まれ、上京して東京美術学校西洋画科に入学、卒業後は渡仏しパリのアカデミーに学んだ。大正13年に帰国したが、翌年の父の死により帰郷を余儀なくされ、昭和2年に再 ...
-

-
秋田県の洋画家の草分け的存在・小西正太郎
2021/7/6
秋田県人で最も早く洋画を学んだとされるのは、男鹿市出身の斎藤鹿山(1866-1943)だが、斎藤は、その後30歳の時に福田笑迎と秋田新聞を創刊、節堂などの筆名で雑文や短編小説を連載するなど、文筆家の道 ...
-

-
日本画革新の旗手であり、故郷を想うロマンチストでもあった福田豊四郎
2021/7/6
秋田県北部の鉱山の町・小坂に生まれた福田豊四郎(1904-1970)は、15歳で画家を志し、17歳で東京の日本画家・川端龍子に師事した。2年後には、龍子の勧めで京都に行き土田麦僊に師事した。豊四郎は、 ...
-
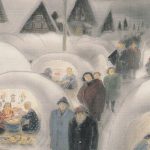
-
秋田の風物を軽妙な筆致で描いた館岡栗山
2021/7/6
館岡栗山(1897-1978)は、馬川村(現在の五城目町)の農家に生まれ、秋田師範に入ったが病弱だったため1年たらずで中退、京都に出て、昭和3年から近藤浩一路に師事した。昭和8年院展に初入選し、師の浩 ...