-

-
緻密な時代考証を加えた歴史画を手掛けた荻生天泉
2021/7/6
福島県安達郡太田村荻ノ田(現在の東和町)に生まれた荻生天泉は、下太田尋常小学校、二本松高等小学校を経て、安積中学校に進んだ。当時の安積中学校には、林竹治郎をはじめとした東京美術学校で学んだ画家たちが美 ...
-

-
大正新南画の中心作家として活躍した湯田玉水
2021/7/6
湯田玉水(1879-1929)は、明治12年、福島県南会津郡田島町(現在の南会津町)に生まれた。田島は明治の廃藩置県で福島県になったが、かつては幕府の直轄地で、北関東と商業的な交流などもあり、独特の文 ...
-

-
福陽美術会を組織し、福島県の日本画の普及と向上に貢献した勝田蕉琴
2021/7/6
福島県棚倉町の士族の家に生まれた勝田蕉琴(1879-1963)は、はじめ会津の画家・野出蕉雨について日本画の基礎を学び、その後上京して橋本雅邦に師事、その翌年東京美術学校日本画科に入学した。同校卒業後 ...
-
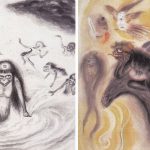
-
喜多方美術倶楽部の結成と小川芋銭
2021/7/6
藩制時代から政治・文化の中心だった会津の北方に位置する喜多方地方は、商人の町として栄え、明治末から大正期にかけては、当時わが国を代表する画家たちがしばしば訪れ、ある時は長期に滞在して制作活動を行なって ...
-
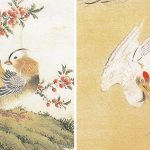
-
小荒井豊山と明治期の喜多方地方の画家
2021/7/6
小荒井豊山(1858-1908)は、安政年間に四条派の絵師だった小荒井輪鼎の子として生まれ、幼いころから父に画を学び、のちに上京して滝和亭に師事した。和亭の私塾に6年間在席し、同門の高弟と称されるよう ...
-

-
太夫と才蔵が面白おかしく掛け合いをする「会津万歳」をこよなく愛し、万歳の画家とも呼ばれた坂内文石
2021/7/6
猪苗代湖畔の湊村に生まれた坂内文石(1865-1930)は、14歳の時に本郷の陶画師・水野雪渚に絵の手ほどきを受け、師の勧めで本郷焼の陶画の仕事に就いた。さらに四条派の遠藤霞村にも画法を学んだ。明治3 ...
-

-
12歳で体験した戊辰戦争を語り伝え、「白虎隊自刃之図」を描いた佐野石峰
2021/7/6
会津に生まれた佐野石峰(1857-1942)は、幼いころから藩の北素読所に入って漢学を修め、のちに橋爪助次郎、福田為之進に詩文を学んだ。明治4年に青森県の三ノ戸学校に入学、かたわら吉越梯雲に北画を学ん ...
-
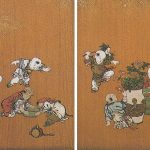
-
遠藤香村に師事し、晩年は東京で活動した渡辺東郊
2021/7/6
渡辺東郊(1848-不明)は、会津若松城下屋敷町に生まれた。祖父光蔵は、武をもってきこえ、特に柔術をよくし、屋敷内に修練所を設けて多くの青年を薫陶していた。しかし、東郊は、生来虚弱体質で、少年の頃は刀 ...
-
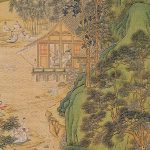
-
復古大和絵を学び、のちに谷文晁門下の高久靄厓の後を継ぎ、大和絵と南画を融合した画風を確立した高久隆古
2021/7/6
高久隆古〔高隆古〕(1810-1858)は、文化7年に忍城下(現在の埼玉県行田市)に阿部家の家臣・川勝隆任の子として生まれた。阿部家は三河以来の徳川家譜代大名として福山の阿部家とともに老中を出す家柄で ...
-

-
豊麗な「牡丹画」のスタイルを完成させ、特に「牡丹に孔雀図」を得意とした野出蕉雨
2021/7/6
会津若松城下の武士の家に生まれた野出蕉雨(1847-1942)は、画を好み、15歳ごろから同じ会津藩士である塩田牛渚について南画を学んだ。藩主・松平容保が京都守護職として在任中は、藩命をもって京都に出 ...
-

-
浦上春琴に師事し長崎三画人にも学んだ塩田牛渚
2021/7/6
会津藩の世臣の子として生まれた塩田牛渚(1828-1866)は、少年の頃には小姓として会津藩主・松平容敬に仕えていたが、幼いころから絵を描くのが好きで、専門絵師になるため、藩士離脱を願い出て職を退き、 ...
-
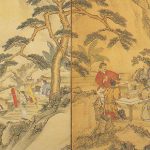
-
和歌もよくした四条派の星暁村
2021/7/6
星暁村は、会津若松城下の城郭外、当時の下町にあたる融通寺町の商家に生まれた。文雅を好み、商売は好まず、幼くして遠藤香村の門に入り、30余年にわたって香村のもとで四条派の技法を学んだ。この間、仙台の松島 ...
-
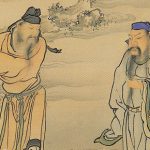
-
会津を離れ彦根藩御用絵師となった佐竹永海
2023/8/9
佐竹永海(1803-1874)は、会津藩の御用もつとめていた蒔絵師の家に生まれた。幼いころから地元の狩野派の絵師・萩原盤山に絵を学び、師から一字を得て「盤玉」と号した。その後、18歳、または20歳の頃 ...
-

-
奇行で知られた会津の狩野派・萩原盤山
2021/7/6
萩原盤山(1772-1846)は、会津若松城下甲賀町に住み、風変わりな行動の絵師として知られていた。路上で犬や鶏に出会うとじっと観察してその場を離れず、近所に火事があれば自らの危険も顧みず我を忘れて火 ...
-

-
会津に初めて西洋画法を伝えた遠藤香村
2021/7/6
南大戸村香塩(現在の会津若松市)の農家に生まれた遠藤香村(1787-1864)は、幼いころから画を好み、会津藩絵師・田村観瀾に狩野派を学んだとされるが、経歴には不詳な点が多い。文化年間、江戸や京都、大 ...
-

-
幼いころから亜欧堂田善の実家に出入りし一番弟子となった遠藤田一
2021/7/6
須賀川加治町の商家・恵比須屋に生まれた遠藤田一(1765-1834)は、幼いころから絵を好み、隣町で染物屋を営んでいた亜欧堂田善の実家に出入りし、田善や兄の永田崑山に絵の手ほどきを受けた。雅号の「田一 ...