-

-
北米で活躍したポール・ホリウチ
2021/7/12
山梨県河口湖町に生まれたポール・ホリウチ(1906-1999)は、15歳の時に両親の移民先である米国に呼び寄せられ渡米した。ワイオミング州のユニオン・パシフィック鉄道に職を得たが、日米大戦中の昭和17 ...
-

-
山梨美術協会の結成
2021/7/7
昭和12年、在京、県内在住者を含めた山梨県出身の美術家たちが、日本画、洋画、彫刻のすべてを網羅して「山梨美術協会」が結成され、東京新宿の高野フルーツパーラーで発会式が挙行された。 当夜の出席者は、県内 ...
-
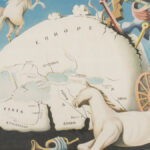
-
米倉寿仁と山梨の前衛絵画団体
2021/7/5
昭和4年、山梨師範学校出身の小柳津経広、中村宗久、田中常太郎らが提唱し、これに太平洋美術学校出身の砂田正己、内田一郎らが呼応して集結し、さらに在京の埴原久和代、土屋義郎、橋戸素視、金子保、小俣球一、金 ...
-

-
山梨県内の洋画黎明期の画家
2021/7/5
山梨県出身の洋画家としては、明治初期に活躍した中丸精十郎をはじめ、女性初の二科会友となった埴原久和代や渡仏して学んだ石原長光らがいるが、山梨県内で洋画団体が結成され、制作活動が活発になってくるのは、大 ...
-

-
渡仏していた絶頂期に失明した石原長光
2021/7/5
石原長光(1886-1950)は、山梨県東八代郡竹原村(現在の笛吹市)に生まれた。17歳で上京し、神田の語学学校で英語を学ぶかたわら白馬会絵画研究所に入所、黒田清輝、和田英作らに師事し、葵橋研究所時代 ...
-

-
女性初の二科会会友となった埴原久和代
2021/7/5
埴原久和代(1879-1936)は、山梨県中巨摩郡源村飯野新田(現在の南アルプス市)に生まれた。10代で結婚したが間もなく離婚し、再婚せずに洋画の道に進むことを決め、東京女子美術学校(現在の女子美術大 ...
-

-
昭和の役者絵に新時代を築いた名取春仙
2024/12/11
名取春仙(1886-1960)は、山梨県中巨摩郡明穂村(現在の南アルプス市)に生まれたが、生後間もなく父の事業の失敗により一家で東京に移り住んだ。幼いころから絵画に親しみ、11歳頃から日本橋数奇屋町の ...
-
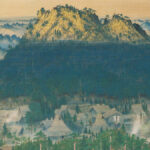
-
山梨の近代日本画の草分けのひとり・古屋正寿
2021/7/5
古屋正寿(1884-1942)は、山梨県東山梨郡七里村(現在の甲州市塩山)に生まれた。明治41年に山梨師範学校を卒業後、上京して東京高等師範図案専修科に入り、在学中から山内多門に日本画を学び、多門没後 ...
-

-
山梨県人で初めて帝展特選をえた大河内夜江
2021/7/5
大河内夜江(1893-1957)は、山梨県東山梨郡大藤村(現在の甲府市塩山)に生まれ、高等小学校を卒業後に上京し、白馬会洋画研究所で洋画を学び、光風会展、日本水彩画会展などに出品した。その後、日本画に ...
-

-
山梨に疎開後は中央画壇から離れた近藤乾年
2021/7/5
近藤乾年(1894-1984)は、南画家・近藤東来(1850-1925)の子として大阪市江戸堀に生まれた。父の東来は旅に生きた絵師で、それゆえに乾年は小学校を15回も転校したという。詳しい経歴は確かで ...
-

-
新興大和絵会の結成に参加した穴山勝堂
2021/7/5
穴山勝堂(1890-1971)は、山梨県東八代郡錦生村(現在の笛吹市御坂町)に生まれた。山梨県立旧制日川中学校を卒業後、上京して東京美術学校師範科に進み、在学中は白馬会に通い洋画家の黒田清輝に学んだ。 ...
-

-
日本画院の創立に尽力した望月春江
2021/7/5
山梨県西山梨郡住吉村増坪(現在の甲府市増坪町)に生まれた望月春江(1893-1979)は、県立甲府中学校(現在の県立甲府第一高等学校)を特待生の成績で卒業し、医者を志して上京したが、美術史家の中川忠順 ...
-

-
洋画から転じ水墨画に新境地を拓いた近藤浩一路
2024/12/11
近藤浩一路(1884-1962)は、山梨県南巨摩郡睦合村(現在の南部町)に生まれ、3歳の時に病弱な父の療養のため一家で静岡県岩渕村(現在の富士市岩淵)に転居した。幼いころから画才を発揮し、韮山中学校( ...
-

-
岡倉天心、横山大観らの渡米に同行した河内雅渓
2021/7/5
山梨県北巨摩郡韮崎町(現在の韮崎市)に生まれた河内雅渓(1873-1943)は、明治27年に上京して橋本雅邦に師事し、東京美術学校日本画科に入学した。しかし明治31年、同校校長・岡倉天心が校内紛争によ ...
-

-
雪舟画に傾倒し雪舟様作品を多く描いた鶴田機水
2021/7/5
明治22年に東京美術学校が開校すると、山梨県下からも同校で学ぶものが出てきた。石和町(現在の笛吹市石和)出身の鶴田機水(1874-1914)は、山梨県尋常中学校(現在の甲府一高)を卒業後、一時教鞭をと ...
-

-
山梨県内に多くの肉筆画を残した浮世絵師・中澤年章
2021/7/5
山梨県巨摩郡布施村(現在の中央市)に生まれた中澤年章(1864-1924)は、22歳の時に上京して浮世絵師・月岡芳年に師事した。どのような経緯で芳年に入門したのかは定かではないが、芳年は甲府を何度か訪 ...