-

-
七尾英鳳と八戸の日本画家
2021/7/6
南部八戸では、藩政時代以来の伝統を持つ日本画の研究会「野の花の会」が、石橋玉僊(1883-1945)を中心に活動を続けていたが、戦争のため中断していた。戦後いち早く発足した美術団体は、昭和22年に考古 ...
-

-
十和田湖に魅せられてその紹介に尽力した鳥谷幡山
2021/7/6
七戸町に生まれた鳥谷幡山(1876-1966)は、函館にいた兄を頼って函館商業学校に入り、当時函館に来ていた寺崎広業と出会い、学校を中退して上京、広業に師事した。幡山が、愛してやまなかった十和田湖を初 ...
-
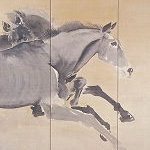
-
画壇を離れ水墨画の原点を追求した野沢如洋
2021/7/6
明治期の津軽地方で、最も優れた画家と評され、広く名を馳せたのは、馬を好んで描き「馬の如洋」とも称された野沢如洋(1865-1937)だった。弘前に生まれた如洋は、当時の津軽画人の第一人者・三上仙年に画 ...
-

-
南部八戸で晩年を過ごした盛岡藩を代表する南画家・橋本雪蕉
2021/7/6
岩手県花巻の呉服商の家に生まれた橋本雪蕉(1802-1877)は、少年時代に花巻の寺小屋師匠で絵師だった八重樫豊澤に画法を学んだ。師の豊澤は、文人墨客との交わりが広く、谷文晁をはじめ多くの画人たちと交 ...
-

-
戦後の青森日本画壇の長老として活躍した高橋竹年
2021/7/6
高橋竹年(1887-1967)は、幼いころから筆を持ち、弘前藩の儒者だった父・米州の薫陶を強く受け、父も学んだ三上仙年に入門、7歳で京都で開かれた大博覧会に出品し、その非凡さが賞賛された。弘前高等小学 ...
-
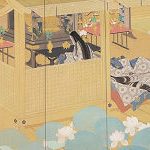
-
平家物語を主なテーマにした蔦谷龍岬
2021/7/6
弘前市の造花店に生まれた蔦谷龍岬(1886-1933)は、弘前尋常高等小学校を出るとすぐに別家すじの造花店に見習い奉公に出されたが、どうしても絵を描きたくて、父の造花の弟子だった一戸や橘平蔵をたよって ...
-
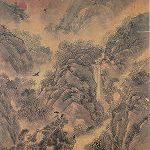
-
津軽初の本格的な女性絵師・工藤晴好
2021/7/6
津軽初の本格的な女性絵師とされる工藤晴好(1867-1924)は、はじめ弘前で三上仙年に学び、その後上京して奥原晴湖の塾に入り、晴湖の養女・晴翠に学んだ。奥原晴湖は、明治初期を代表する女傑といわれた画 ...
-

-
悠々自適に書画に親しんだ弘前藩士・棟方月海
2021/7/6
明治維新の動乱期に軍政で活躍し、大隊長をつとめた弘前藩士の棟方月海は、廃藩置県後の動向については不明な点が多いが、酒を楽しむ悠々自適の生活を送り、書画に親しんだとされる。画の師は定かではないが、三上仙 ...
-

-
平尾魯仙門下で三上仙年と双璧とされた工藤仙乙
2021/7/6
平尾魯仙の門人で、三上仙年と並び称されたのが工藤仙乙(1839-1895)である。仙乙は、幼いころから画を好み、長年魯仙の元で画を学び、その技量は三上仙年を凌ぐともいわれた。はじめは山水画を好み、諸国 ...
-
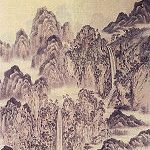
-
平尾魯仙の高弟・三上仙年
2021/7/6
平尾魯仙の門人たちによって、明治期の津軽の日本画は大きな進展を遂げるが、なかでも高弟といわれた三上仙年と工藤仙乙は、明治30年代に弘前絵画会という日本画団体を設立し、弘前における日本画の普及と発展につ ...
-

-
幕末維新期の津軽画壇をリードした平尾魯仙
2021/7/6
毛内雲林と松宮岱陽によって津軽に広められた南画は、松山雲章、工藤五鳳に引き継がれ、その門人たちによってさらに広められていった。なかでも平尾魯仙の出現は、江戸時代から近代へとつながる津軽画壇の基盤を確固 ...
-
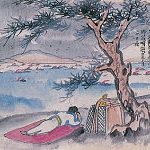
-
放浪の画人・蓑虫山人が描いた明治の青森
2021/7/6
幕末から明治にかけて全国を放浪した画人・蓑虫山人(1836-1900)は、美濃国(現在の岐阜県)に生まれ、14歳で故郷を出て全国を歩き、各地に足跡を残している。旅先では絵を描き、古遺物を収集し、多くの ...
-
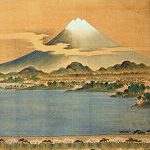
-
津軽各地の情景を描いた儒者・百川学庵
2021/7/6
儒者の家系に生まれた百川学庵(1799-1849)は、儒学、詩文にすぐれ、画は江戸で谷文晁に学んだ。学庵の父親・百川玉川は、江戸で太田錦城に学び、21歳で藩校稽古館の助教授になった優れた儒者だったが、 ...
-

-
八戸に俳画を広めた浮世絵師・魚屋北渓
2024/12/11
八戸藩七代藩主・南部信房は、風雅を愛し、俳人としてもよく知られた。信房の周辺には狩野派の絵師や浮世絵師が出入りしていたが、八戸藩の家臣の家禄をまとめた「身帯帳」には「御絵師」の肩書のある人名が見当たら ...
-

-
現存する最古のねぷた絵を描いた小島左近
2021/7/6
弘前のねぷた祭は、毎年8月1日から一週間に渡って繰り広げられる青森を代表する夏祭りで、扇型の「扇ねぷた」や人形型の「組ねぷた」を押したて、日没とともに目抜き通りを練り歩く。各ねぷたには、絵師たちが腕を ...
-

-
狩野派を学んだ弘前藩士・今井玉慶
2021/7/6
藩のお抱え絵師は、国元の藩士にも絵を教えたが、狩野派の描法で画家として名を成すものは、きわめて稀だった。大浦城跡のある賀田に生まれ、藩の狩野派絵師・今村惟慶に師事した今井玉慶は、賀田の玉慶として親しま ...