-

-
最後の近代歴史画家・羽石光志
2021/7/6
近代歴史画の父・小堀鞆音が開拓した新しい歴史画は、安田靫彦や前田青邨ら多くの画家たちによって引き継がれていったが、時の流れとともに日本画は新しさを求めて多様化していき、歴史画は次第に画家たちの興味の対 ...
-

-
抽象表現に南画の新しい境地を拓いた大山魯牛
2021/7/6
大山魯牛(1902-1995)は、東京日本橋に生まれ、生後すぐに実家のある足利に移った。3歳の時に病気のため右足を切断し、手術時の後遺症で左耳の聴覚を失った。10歳頃から本家の所蔵品の虫干しを手伝いな ...
-

-
視力を失ってからも描き続けた長谷川沼田居
2021/7/6
長谷川沼田居(1905-1983)は、現在の足利市県町に生まれた。15歳で田崎草雲の門人・牧島閑雲の内弟子となり、南画の基礎と漢学を学んだ。20歳の時に上京し、ニコライ堂の牧師で洋画家だった閑雲の子・ ...
-

-
イコンと仏画を融合した独自の宗教画を確立した牧島如鳩
2021/7/6
牧島如鳩(1892-1975)は、南画家・牧島閑雲の長男として現在の足利市上渋垂町に生まれた。父が熱心なハリストス正教徒だったことから、如鳩も幼児洗礼を受け聖名パウエルを授けられた。明治41年、東京神 ...
-
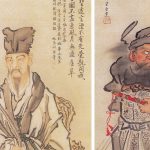
-
南画を描きながら足利の青年たちに漢学を教えた牧島閑雲
2021/7/6
牧島閑雲(1851-1942)は、栃木県梁田郡梁田宿(現在の足利市梁田町)に生まれ、9歳頃から館林藩の儒臣・田中泥斎に漢学を学んだ。22歳の時に田崎草雲に師事し、以後20年間にわたり草雲の指導を受け、 ...
-

-
明治最初期に師範学校の図画教員を長くつとめた河野次郎
2021/7/6
河野次郎(1856-1934)は、足利藩の江戸藩邸に生まれ、明治時代最初期の美術教育者として師範学校の図画教員を長くつとめた。教え子には中村不折や結城素明らがいる。大正から昭和初期にかけて活躍した河野 ...
-

-
ニューヨークで食器デザインと油彩を手がけた古田土雅堂
2021/7/6
栃木県芳賀郡中川村(現在の茂木町)に生まれた古田土雅堂(1880-1954)は、上京して東京美術学校日本画科に学び、卒業して間もなくアメリカに渡った。シカゴで働きながら美術を学び、翌年にはニューヨーク ...
-

-
20世紀初頭のアメリカで独自の画風を確立させた清水登之
2021/7/6
清水登之(1887-1945)は、栃木県下都賀郡国府村(現在の栃木市)の大地主の家に生まれた。絵画好きの父の影響で、子どものころから絵に親しみ画家になる夢も持っていたが、中学の先生の勧めもあり、軍人を ...
-
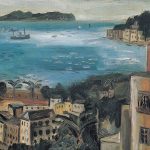
-
日本画壇とパリ画壇の双方で活躍した川島理一郎
2021/7/6
足利市に生まれた川島理一郎(1886-1971)は、幼いころから母の実家がある東京で育った。19歳のときにニューヨークで雑貨商を営む父を頼って単身渡米、パブリック・スクールを卒業後は、父の仕事を手伝い ...
-
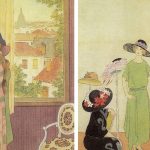
-
初期文展で活躍し挿絵や口絵も多く手がけた橋本邦助
2024/12/11
栃木町(現在の栃木市)の紙類商の家に生まれた橋本邦助(1884-1953)は、17歳で東京美術学校西洋画科選科に入学し黒田清輝に師事した。入学後の成績が優秀だったため1年級終了後4年級に進級し、明治3 ...
-

-
青木繁と福田たね
2024/12/11
明治画壇を駆け抜け、夭折の天才画家とも称される青木繁の生涯と芸術を語るとき、恋人・福田たねの存在を忘れることはできない。ともに重要文化財である青木の代表作「海の幸」も「わだつみのいろこの宮」も、たねと ...
-

-
洋画から日本画に転じ脱俗の精神を貫いた小杉放菴
2024/12/11
日光の神官の子として生まれた小杉放菴(1881-1964)は、15歳の時に中学校を中退し、日光に住んでいた初期洋画家の五百城文哉の内弟子となった。師の文哉は水戸出身で、江戸で高橋由一に学び、晩年は日光 ...
-
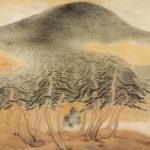
-
写実性や装飾性を取り入れた異端の南画家・石川寒巌
2021/7/6
栃木県黒羽町(現在の大田原市)に生まれた石川寒巌(1890-1936)は、早くから文学や美術に興味を持ち、19歳で上京、太平洋画会研究所で油彩画を学ぶとともに、佐竹永邨について南画を学んだ。しかし、念 ...
-
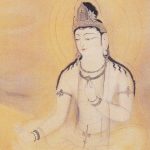
-
古典研究とインド体験による独自の仏画を完成させた荒井寛方
2025/3/27
栃木県氏家町(現在のさくら市)に生まれた荒井寛方(1878-1945)は、明治32年に上京し、浮世絵師・水野年方に入門、歴史画、風俗画を学んだ。同門には鏑木清方、池田輝方、大野静方らがおり、のちに寛方 ...
-

-
全国各地を放浪のすえ佐野に定住した南画家・王欽古
2021/7/6
京都の医師の家に生まれた王欽古(1830-1905)は、小田海僊に師事し、師の画風を受けて南画山水を得意とした。はじめは海雲と号していたが、のちに中国の士大夫をきどって王欽古と号したという。江戸に出て ...
-

-
近代歴史画の父・小堀鞆音
2024/12/11
現在の佐野市に生まれた小堀鞆音(1864-1931)は、20歳頃に上京、土佐派の川崎千虎について歴史画を学んだ。明治25年には岡倉天心を会頭とする日本青年絵画協会に創立会員として参加。明治30年東京美 ...