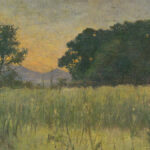櫻井忠剛「落ち葉をかく人」
櫻井忠剛(1867-1934)は、尼崎藩主松平家(維新後に櫻井と改姓)分家の松平忠顕の二男として生まれた。明治9年上京して勝海舟のもとに寄寓し、勝邸内で画塾を開いていた川村清雄に洋画を学び、池田口南に南画を学んだ。
明治27年尼崎に戻り、同年松原三五郎、山内愚僊、松本硯生(不明-不明)らと関西美術会(第1次)を結成した。明治30年頃京都に移住し、以降新古美術品展に出品し、明治34年の第3次関西美術会結成の際には京都側委員として田村宗立、伊藤快彦らとともに参加した。
明治35年頃に東山霊山明烏温泉東にアトリエを新築したが、明治36年頃に尼崎に帰り、明治38年には請われて尼崎町長となった。尼崎が町から市に昇格後は、初代尼崎市長として大正5年から大正11年までつとめ、昭和3年から再び尼崎市長に就任したが昭和9年在職中に死去した。
櫻井忠剛(1867-1934)さくらい・ただたか
慶応3年生まれ。尼崎藩主桜井松平家の一族。号は天華。明治9年上京。中村敬宇の同人社、および攻玉社に学んだ。勝海舟のもとに寄寓し勝邸内画塾を開いていた川村清雄から洋画を学び、また、池田口南に南画を学んだ。明治27年に尼崎に帰り、同年関西美術会(第1次)創立に参加。明治30年頃京都に移住。以降新古美術品展に出品し、明治31年第4回展で審査員をつとめ、翌年の第5回展に出品、第6回展では3等賞、第7回展では2等賞を受賞した。明治34年関西美術会(第3次)創立に参加。明治35年頃に東山霊山明烏温泉東にアトリエを新築。明治36年頃尼崎に帰郷。明治38年には請われて尼崎町長となり、大正5年から大正11年と昭和3年から昭和9年まで尼崎市長をつとめ、在職中の昭和9年、68歳で死去した。

松本硯生「櫻井豊子像」
松本硯生(不明-不明)まつもと・けんせい
詳しい経歴は不明だが、明治27年大阪で最初の関西美術会(第1次)結成の試みがあった時、櫻井忠剛とともに出席している。掲載の「櫻井豊子像」には「明治31年写之」の年記があり、豊子は櫻井の妻であることから、櫻井と近しい関係にあった人物と思われる。明治34年の関西美術会(第3次)の大阪側の発起人をつとめた。
大阪(103)-画人伝・INDEX
櫻井忠剛と関西洋画の先駆者たち: 洋画の先駆者にして初代尼崎市長、浅井忠と関西美術院展