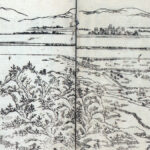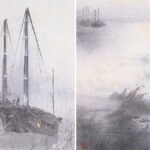平井直水「梅花孔雀図」
平井直水(1860-不明)は、30歳で画家を志し深田直城に師事した。孔雀を描くのを得意とし、日本絵画協会などで受賞を重ね、明治40年に日本初の官展として開設された文展の第1回展では大阪唯一の入選者となった。また、大阪美術展覧会で鑑査員をつとめ、大正美術会に反する大同会に深田直城とともに参加した。
ほかに深田直城の門人としては、長男の深田五城をはじめ、大塚春嶺、伊藤直應、久城月、中川和堂、木谷千種らがいる。
平井直水(1860-不明)ひらい・ちょくすい
安政7年大坂生まれ。名は豊、字は子邦、通称は虎之助。別号に静斎、夏月樓がある。深田直城に師事した。山水花鳥に長じ、特に孔雀を得意とした。明治26年日本青年絵画協会第2回絵画共進会に出品。明治27年同第3回絵画共進会で3等褒状。明治28年同第4回絵画共進会で3等褒状。明治29年日本絵画協会第1回絵画共進会で2等褒状。明治30年同第2回絵画共進会で2等褒状。同年同第3回絵画共進会で2等褒状。明治31年同第4回絵画共進会にも出品するなど、各展覧会で受賞を重ねた。明治33年パリ万博出品。明治37年セントルイス万博で銀賞。明治40年第1回文展入選。大正4年第1回大阪美術展覧会で鑑査員をつとめ、大同会に深田直城と参加。大正年間に死去した。
大塚春嶺(1861-1944)おおつか・しゅんれい
文久元年丹波国船井郡園部村生まれ。名は宗秀、字は子克、通称は勝之助。小林家の長男として生まれ、大塚家の養子となって大阪に住んだ。明治23年深田直城に師事。明治29年頃からは京都の谷口香嶠に学び、歴史有識風俗画を得意とした。明治27年日本青年絵画協会第3回絵画共進会で2等褒状。明治28年第4回内国勧業博覧会で褒状を受け、明治天皇買上げ。明治36年第5回内国勧業博覧会で褒状。明治38年日本美術協会主催の展覧会に出品。晩年は画室を建てて園部で暮らした。昭和19年、83歳で死去した。
久城月(1883-不明)ひさ・じょうげつ
明治16年大阪府北河内郡大和田村(現在の門真市)生まれ。尾張に起源を持つ旧家・西邨家の二男。本名は一雄、字は孝延。11歳の時に親戚である堺の久家の養子となった。21歳の時に深田直城に師事。妻は直城の二女。また、菊池芳文に師事して花鳥人物を得意とした。第9回文展に入選。昭和11年の時点で西宮に居住。昭和13年阪急百貨店で美人画展を開催した。
中川和堂(1880-不明)なかがわ・わどう
明治13年大阪生まれ。名は孝清、通称は忠次郎、字は伯順。別号に宜月樓無外、朴素などがある。父の中川芝泉は芝川家と住友家が共同出資で設立した蒔絵会社の教授をつとめた。11歳の時に深田直城に入門して芦城と号した。また父から蒔絵を学んだ。明治32年和堂に改号し、京都に出て菊池芳文に師事した。その後両親が相次いで没したため須磨の芝川家の別荘に3年ほど住み、田能村直入に師事して南画を学んだ。明治40年深田直城を仮親として平井直水の媒酌によって中川蘆月の養嗣子となり大阪に住んだ。北野恒富らと大阪美術展覧会を設立、墨土社の同人として活躍するとともに白毫社を主宰した。
大阪(93)-画人伝・INDEX
文献:大阪の日本画、日本美術院百年史1巻上、上島鳳山と大阪の画家たち