-

-
平井直水、大塚春嶺ら深田直城の門人
2025/3/28
平井直水「梅花孔雀図」 平井直水(1860-不明)は、30歳で画家を志し深田直城に師事した。孔雀を描くのを得意とし、日本絵画協会などで受賞を重ね、明治40年に日本初の官展として開設された文展の第1回展 ...
-

-
姫島竹外に学び花鳥画を得意とした山田秋坪
2025/3/14
山田秋坪「柘榴花白鸚鵡図」 山田秋坪(1877-1960)は、豊前国の中津藩士の家に生まれ、幼くして大阪に転居した。父の秋溪(秋佳)に南画と漢学を学び、父の没後は姫島竹外に師事した。日本青年絵画協会展 ...
-

-
跡見学園の一期生となり花蹊に書画を学んだ波多野華涯
2025/3/7
波多野華涯「三白図」「玉蘭海棠図」 波多野華涯(1863-1944)は、元水戸藩士で銅の商人をしていた波多野善四郎の長女として大坂に生まれた。単身上京し、明治8年に跡見花蹊が神田猿楽町に開校した跡見学 ...
-

-
沈南蘋の影響を受け極彩色の花鳥画を残した泉必東
2024/10/2
泉必東「花鳥図」 泉必東(不明-1764)は、清人銭氏の子孫と伝わっており、『要略』では銭必東と記されている。幼少の頃から画を好み、諸国を遊歴して画技を磨き、特に沈南蘋の影響を受けて山水花鳥を得意とし ...
-

-
興福院や円照寺に襖絵が残っている渡辺始興
2024/6/5
渡辺始興「農夫図屏風」東京国立博物館 渡辺始興(1683-1755)は、尾形光琳に学んだ光琳派の画家として知られるが、絵巻の研究によって大和絵系の筆法も学び、狩野尚信を慕って狩野派の骨法にも習熟し、晩 ...
-

-
濱田観ら竹内栖鳳に学んだ兵庫県ゆかりの日本画家
2024/3/22
濱田観「花芥子」姫路市立美術館蔵 京都で竹内栖鳳に師事した兵庫県ゆかりの日本画家としては、橋本関雪、森月城、三木翠山、立脇泰山、村上華岳のほか、宮崎翠濤、松井香瑤、土肥蒼樹、山本紅雲、濱田観、中田晃陽 ...
-
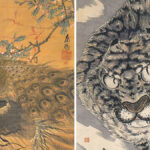
-
江戸で殺人を犯し逃亡先の長崎で画を学んだ島琴陵
2024/1/22
島琴陵「海棠孔雀図」 島琴陵(1782-1862)の前半生はよく分かっていないが、もと南部藩士で、江戸で人を殺して出奔し、逃亡先の長崎で来舶清人らと交遊して画を学んだと伝わっている。長崎派の写実的な花 ...
-

-
抱一の後継者として画房・舫雨華庵を継いだ酒井鶯蒲
2024/12/11
酒井鶯蒲「四季草花図雛屏風」 酒井抱一によって江戸に定着した光琳様式は、洗練の度を加えて江戸琳派に発展した。抱一のもとには作画の注文が殺到し、抱一の住居兼画房の「雨華庵」には、早世した一番弟子の鈴木蠣 ...
-

-
鈴木鶏邨、田中抱二ら抱一工房を支えた門人たち
2024/1/12
鈴木鶏邨「秋草に小禽図」細見美術館蔵 酒井抱一の門人としては、最初期の弟子である鈴木蠣潭、江戸琳派様式の拡大に貢献した鈴木其一、其一と並び称される高弟の池田孤邨らが知られているが、ほかにも寡作ながら抱 ...
-

-
江戸琳派と呼ばれる独自の画風を確立した酒井抱一
2024/12/11
酒井抱一「秋草鶉図」山種美術館蔵 酒井抱一(1761-1829)は、徳川家重臣の名門大名家である酒井家の15代家主忠恭の二男として江戸神田小川町の酒井家別邸に生まれた。代々風雅を愛した酒井家にあって、 ...
-

-
風雅を好んだ姫路藩主・酒井宗雅
2024/1/5
左:酒井宗雅「兎図」兵庫県立歴史博物館蔵、右:酒井宗雅「石楠花に山鳩図」 酒井宗雅(1755-1790)は、名を忠以といい、姫路藩主酒井忠恭の嫡子・酒井忠仰の長男として姫路藩の江戸藩邸に生まれた。酒井 ...
-

-
播州龍野の円山派・山村翠谷
2023/12/25
山村翠谷「薔薇に錦鶏図」 外内松意ら龍野藩につかえた狩野派の絵師に対し、山村翠谷(1787-1850)は、若いころに京都に遊び、円山派を学んだ。一説には応挙門下十哲のひとり・奥文鳴に師事したという。家 ...
-

-
明石の近世画人・岡田東虎と林半水
2023/12/20
岡田東虎「八相涅槃図」信州松本・宝栄寺蔵 岡田東虎(1755-1822)は、明石城下西本町(現在の明石市)の旅宿「井筒屋」の子として生まれた。はじめ西宮の勝部如春斎に学び、福原五岳にもつき、のちに大坂 ...
-

-
兵庫津に移り住んだ長崎派の画人・斎藤雀亭
2023/12/7
左:斎藤雀亭「菊に叭々鳥図」、右:斎藤雀亭「牡丹岩小禽図」 斎藤雀亭(1737?-1812)は、長崎出身で兵庫津に移り住み、岡方の魚棚町で医者を業としながら画を描いていたと思われる。菩提寺である神戸市 ...
-

-
松村景文門下随一の技量とうたわれた長谷川玉峰
2023/8/18
長谷川玉峰「老松孔雀図」 長谷川玉峰(1822-1879)は、画家の長谷川玄門の子として京都に生まれ、四条派の松村景文に師事した。師の景文は、四条派の祖である松村呉春の弟で、玉峰は景文にとって晩年の弟 ...
-

-
郷里で自由な作画を続けた湖東の円山派・林東溪
2023/8/16
林東溪「花籠図」 林東溪(1807-1887)は、近江国蒲生郡中野村(現在の東近江市)に生まれた。幼いころから学問を好み、特に画を描くことを好んだという。成長するにしたがって、画を学ぶとともに易経・天 ...