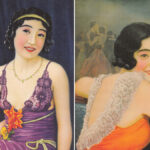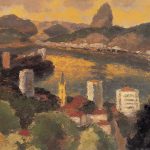鈴木亜夫「ラングーンの防空とビルマ人の協力」東京国立近代美術館(無期限貸与作品)
鈴木亜夫(1894-1984)は、工学博士・鈴木幾弥太の二男として大阪に生まれた。少年のころ東京に転居し、葵橋洋画研究所を経て東京美術学校西洋画科に進学、藤島武二らの指導を受けた。同校在学中に二科展に入選し、昭和3年には会友となったが、昭和5年には二科を脱退し、里見勝蔵らと独立美術協会を創立した。同展には、指導的立場として没するまで出品を続けた。
戦時下の昭和16年には陸軍からビルマ(現在のミャンマー)に派遣され、記録画制作に携わった。掲載の「ラングーンの防空とビルマ人の協力」はその際に描かれたもので、昭和19年の陸軍美術展に陸軍作戦記録画として出品された。この作品は、ビルマが連合軍の反攻にさらされ、戦局が悪化していった頃のもので、空襲を受けた首都ラングーンにおけるビルマ人看護師たちの勇敢な活躍ぶりが描かれている。
鈴木亜夫(1894-1984)すずき・つぎお
明治27年大阪府生まれ。明治45年芝中学校に入学、葵橋洋画研究所に学び東京美術学校西洋画科に進学した。大正5年第3回二科展に入選。大正10年東京美術学校を卒業し、同研究科に進み藤島武二に師事した。昭和3年二科会会友となった。昭和4年一九三〇年協会に参加。昭和5年伊藤廉、川口軌外、小島善太郎、児島善三郎、里見勝蔵、清水登之、鈴木保徳、高畠達四郎、中山巍、林重義、林武、福沢一郎、三岸好太郎と独立美術協会を創立。昭和16年陸軍美術会で記録画の担当となり戦争画を描いた。昭和59年、90歳で死去した。
大阪(147)-画人伝・INDEX
文献:戦争と美術、実力画家たちの忘れられていた日本洋画2