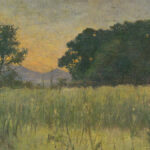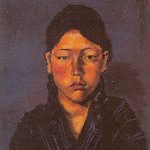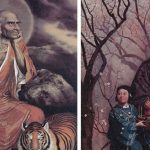山内愚僊「住吉神社」笠間日動美術館蔵
大阪洋画の草創期に活躍した画家としては、浮世絵の月岡芳年門下の鈴木蕾斎(不明-不明)が知られるが、本格的に大阪で洋画がはじまるのは、山内愚僊、松原三五郎が相次いで大阪に移り住んでからといえる。
山内愚僊(1866-1927)は、江戸に生まれ、高橋由一、五姓田芳柳、渡辺文三郎に西洋画法を学んだ。大阪を訪れたのは明治22年頃で、大阪朝日新聞社に入社して挿絵を担当し、そのかたわら大阪市立大阪高等商業学校の図画教師もつとめ、内弟子の赤松麟作や山本森之助らを東京美術学校に進学させるなど後進の指導にもつとめた。
また、明治25年に松原三五郎とともに大阪府立博物場で大阪初とされる洋画展を開催した。明治27年には松原とともに大阪で関西美術会(第一次)を結成し、明治34年に京都で関西美術会を結成するなど、大阪洋画壇の先駆者として活躍した。
山内愚僊(1866-1927)やまのうち・ぐせん
慶応2年江戸生まれ。本名は真郎、あるいは貞郎。初号は愚仙、のちに愚僊に改号。高橋由一、五姓田芳柳、渡辺文三郎に西洋画法を学んだ。明治20年東京府工芸共進会に出品。西村天囚と連れ立って関西に移り、明治22年大阪朝日新聞社に入社、挿絵を担当した。明治25年松原三五郎とともに大阪で洋画展を開催。明治27年松原と大阪で関西美術会(第1次)を結成。明治29年関西美術会(第2次)展を開催。明治34年京都で関西美術会(第3次)を結成した。同年関西美術会第1回批評会で牧野克次の作品とならび1等賞を受賞し、以後同会で活躍した。明治36年第5回内国勧業博覧会に出品。明治44年から翌年にかけて渡欧、大正初期には朝鮮を訪れた。昭和2年、62歳で死去した。
参考記事:UAG美人画研究室(山内愚僊)

鈴木蕾斎「大井川渡しの図」神戸市立博物館蔵
鈴木蕾斎(不明-不明)すずき・らいさい
大坂の人。月岡芳年の門人。名は雷之助。別号は年基。浮世絵師だが、油彩をどのように学んだかは不明。
大阪(100)-画人伝・INDEX
文献:京都洋画の黎明期、油絵の大阪 : 商都に生きた絵描きたち、浅井忠と関西美術院展、明治の洋画、洋画家たちの明治