-

-
関東に本格的な水墨画をもたらした室町時代の画僧・祥啓
2021/7/6
祥啓「山水図」根津美術館蔵 祥啓(不明-不明)の出自については不明な点が多く、生まれは真壁郡下館(現在の筑西市)とも常陸小田(現在のつくば市)ともされ、野州宇都宮の画家丸良氏の子として、現在の栃木県宇 ...
-

-
庄内地方を代表する画僧・市原円潭
2021/7/6
市原円潭「閻魔王宮八大地獄図(十王図)」3幅のうち左幅部分 鶴岡・常念寺蔵 酒田の商家に生まれた市原円潭は、幼いころから絵に興味を示し、15歳で江戸に出て、24歳から28歳まで狩野探淵守真のもとで狩野 ...
-
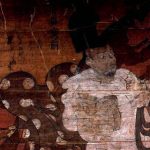
-
山形県で最も早く名前が登場する画人・郷目貞繁
2021/7/6
郷目貞繁「神馬図絵馬」(重文)天童市・若松寺蔵奉納銘に「観音御宝前 奉納馬形 旦那郷目右京進妻女菩薩故也 寒河江内郷目右京進貞繁(花押)干時永禄六年葵亥九月十八日」とあることから、永禄6年に画家自身が ...
-

-
肥後の画僧・豪潮と宇土藩主・細川月翁
2024/12/21
豪潮「文殊菩薩騎獅図」 肥後出身の天台宗の高僧・豪潮(1749-1835)は、書画もよくした。豪潮は天台宗の僧だが、その画題には、禅宗的(釈迦三尊や羅漢図)なものが多くみられる。これは豪潮が交友した珍 ...
-

-
宮本武蔵ら余技の画人
2021/7/6
伝宮本武蔵「芦雁図屏風」 肥後熊本藩をおさめていた加藤家や細川家は、全国的にも有名な大名であり、文化的な素養も備えていた。そのため、著名な学者や兵法者を周辺に集め、また自然に集まりもした。加藤家におけ ...
-

-
武人画家・宮本武蔵
2021/7/9
宮本武蔵「布袋観闘鶏図」(重美) 二刀流の剣豪として名高い宮本武蔵(1584-1645)も岡山ゆかりの画人である。「二天」と号して画筆をとり、個性豊かな作品を残している。出生地は美作説のほかに播磨説も ...
-
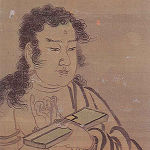
-
土佐派の流れを汲む画僧・鶴洲と讃岐の土佐派
2022/9/3
鶴洲「文殊菩薩図」 讃岐において、狩野派の画僧・實山と並び称されるのが、土佐派の流れを汲む画僧・鶴洲である。後年の活動から鶴洲を土佐派の画人とするには異論もあるが、鶴洲は、住吉派の祖である住吉如慶の子 ...
-

-
狩野派の画僧・實山と高松藩の文人大名
2022/9/3
實山「福禄寿図」 讃岐を代表する画僧・實山も狩野派の画人である。實山は江戸の人で、狩野家の養子となったが、のちに実子が生まれたために僧となり、享保年間は高松の見性寺で住職をつとめ、隠居して自性庵に住ん ...
-

-
庶民の姿や風俗を描いた尾張藩士・高力猿猴庵
2024/12/30
高力猿猴庵「御鍬祭図略」 高力猿猴庵「見世物つくし」 江戸が華やかな庶民文化に湧いていた江戸時代後期、名古屋城下においても文化的繁栄の時代を迎えていた。賑やかな祭りや華やかな行列が街を彩り、芝居、見世 ...