-

-
木谷千種の画塾・八千草会の女性画家たち
2025/6/16
八千草会は、大正9年に木谷千種(参考)が後進の女性画家育成のために大阪の自宅に創立した画塾で、芸術を志す女性が助け合い、男性と伍していくことを理念とした。人物画だけでなく花鳥画も教え、外部講師に美学者 ...
-

-
昭和期における大阪の女性画家の中心的存在・木谷千種
2025/6/13
木谷千種(1895-1947)は、大阪市北区堂島に生まれ、12歳で渡米し、シアトルで洋画を学んだ。2年後に帰国し、大阪府立清水谷高等女学校に通学し、深田直城に師事したが、同校卒業前に上京し、池田蕉園( ...
-

-
養女となった岡本成薫ら島成園に学んだ女性画家
2025/6/11
若くして官展で活躍し全国的に名声を得た島成園(参考) のもとには、各地から弟子志願者が集まり、多くの女性が門下生として学んだ。成園が結婚し、夫の転勤に同行して画壇から離れてからは、一部は中村貞以(参考 ...
-

-
大正期の大阪での女性画家ブームを牽引した島成園
2025/6/9
島成園(1892-1970)は、大阪府堺市熊野町に生まれた。襖絵などを描いていた町絵師の父と画家で図案家でもあった兄のもとで画に親しみ、15歳頃から兄の仕事を補佐しながら独学で画を学んだ。大正元年、2 ...
-

-
清雅な趣をたたえる現代的女性像を描いた中村貞以
2025/6/6
中村貞以(1900-1982)は、大阪市船場に生まれた。はじめ浮世絵師・二代長谷川貞信に画の手ほどきを受け、岡本景邦に運筆や写生を学び、大正8年からは北野恒富に師事した。2歳の時に両手に大火傷を負い、 ...
-
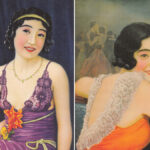
-
大阪商業図案家協会を結成した高木葆翠
2025/6/4
高木葆翠(1894-1947)は、福岡県に生まれ、実家が染物屋を営んでいたことから、幼いころから日本画に親しみ、のちに油絵に興味を持ち、19歳で上京して岡田三郎助に師事した。30歳まで岡田のもとで油彩 ...
-

-
にこやかな中年婦人を描き人気を博した松田富喬
2025/6/2
松田富喬(不明-不明)は、北野恒富に師事し日本画を学んだ。日本画家としては大成しなかったが、師の恒富がポスター分野で人気を博した影響から、1920年代半ばから各種ポスター用図案の懸賞募集に積極的に応募 ...
-

-
恒富風美人画ポスターの後継者と目された樋口富麻呂
2025/5/30
北野恒富(参考)は、大阪の日本画壇の中心人物として活躍する一方で、ポスター制作にも積極的に携わり、美人画ポスター画家としても人気を博し、掲載の「キンシ正宗 堀野醸」など日本のポスター史に残る逸品を多く ...
-
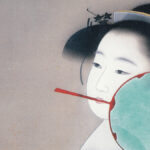
-
北野恒富門下の「雪月花星」
2025/5/28
北野恒富(参考)が大正3年に設立した画塾「白耀社」は、大阪の若手日本画家の研鑽の場として大きな機能を果たした。当時としては珍しく男女共学で、リベラルな雰囲気が魅力で女性会員も多く、女性の割合は4割とい ...
-

-
大阪の人物画の開花に中心的役割を果たした北野恒富
2025/5/26
明治36年、大阪で第5回内国勧業博覧会が開催されると、多数展示された東京の画家たちの作品に刺激され、大阪の画家たちの間でも新しい表現を求める活動が盛んになっていった。その中心的な役割を果たしたのが北野 ...
-

-
歴史的人物や文学に取材した作品を手掛けた福岡青嵐
2025/5/23
福岡青嵐(1879-1954)は、熊本県に生まれ、明治31年、東京浅草の山田敬中を訪問した時に初めて絵筆をとり、以後荒木寛畝に学んだ。昭和36年東京美術学校日本画科を卒業し、その後大阪に移り、一時は大 ...
-

-
関西の都市下層に生きる女性を描いた鳥居道枝
2025/5/21
鳥居道枝(1902?-1930)は、陸軍技師・鳥居榮の長女として東京に生まれ、父の赴任先の大阪で少女期を過ごした。大阪府立清水谷高等女学校を卒業後、岡本大更に師事し、両親の全面的理解のもと絵画の制作に ...
-

-
独学で学び美人画を得意とした岡本大更
2025/5/19
岡本大更(1879-1945)は、三重県名張郡滝之原村に生まれ、幼いころ一家で東京に出た。幼少期から画才を発揮し、評判の子だったという。京都に出て京都府画学校で学んだが中退、その後は特定の師につかず、 ...
-

-
生涯にわたり大阪の歴史風俗を題材とした生田花朝女
2025/5/16
生田花朝女(1889-1978)は、文人で画も描いた生田南水の三女として大阪市天王寺区上之宮町に生まれた。幼いころから諸学を修め、俳句を父に、漢学を藤澤黄坡に、国学を近藤尺天に学んだ。画ははじめ四条派 ...
-

-
その美貌で全国的に知られた芸妓・富田屋八千代
2025/5/14
富田屋八千代(1887-1924)は、大阪府中河内郡西六郷村本庄(現在の東大阪市)の農家・西田家に生まれ、その後、大阪市の宗右衛門町で置屋・加賀屋を営む遠藤家の養女となった。明治30年に妓籍に入ると、 ...
-

-
軽妙洒脱な「浪速風俗画」を確立した菅楯彦
2025/5/12
菅楯彦(1878-1963)は、日本画家・菅盛南の子として現在の鳥取県に生まれ、幼くして一家で大阪に移り住んだ。大阪移住後ほどなくして襖絵の絵師をしていた父が病に伏せたため、楯彦は11歳にして絵師とし ...