-
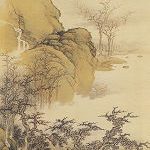
-
衰退する南画の復興をはかり日本南画院を創設した田近竹邨
2021/7/6
江戸後期から全国的な流行をみせた南画だったが、明治中頃になると急速に衰えていった。その要因としては、南画理解に不可欠な漢詩の素養が、時代の推移とともに一般的になくなってきたことや、絵画鑑賞が床の間から ...
-
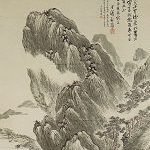
-
杵築南画の創始者・十市石谷と十市家
2021/7/6
杵築の十市家は、杵築南画の創始者と称される十市石谷(1793-1853)をはじめ、子の王洋・古谷、及びその子たちも画をよくした。杵築藩家臣の家に生まれた十市石谷は、幼いころから画に親しみ、中国の名画を ...
-

-
臼杵生まれの挿絵画家・右田年英
2024/12/14
報道錦絵などで人気を博した挿絵画家・右田年英(1862-1925)は臼杵の生まれで、14歳の時に東京に出て、歌川派の月岡芳年の門に学び、水野年方、稲野年恒とともに芳年門の三傑と称されるようになった。芳 ...
-
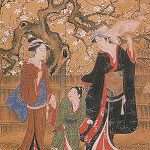
-
歌川派の開祖・歌川豊春はやはり豊後臼杵出身なのか
2024/12/11
歌川豊春は、浮世絵の一大流派である歌川派の開祖にあたり、門下からは、初代豊国や豊広らが出て、さらにその画系からは国貞、国芳、広重など傑出した絵師を多く輩出している。豊春の作画活動においては、初期には春 ...
-
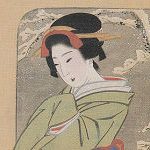
-
国東地方にちょっとした京風美人画ブームをもたらした吉原真龍
2024/12/14
豊後出身の美人画家としては、西国東郡真玉町の吉原真龍(1804-1856)があげられる。真龍は文政期頃に京都に出て三畠上龍に入門し美人画を学んだ。京都を中心に活躍し、嘉永2年には宮中への出入りを許され ...
-

-
幕末三大本草学者のひとり・宇佐の賀来飛霞
2021/7/6
本草学とは、中国医学に付属した薬物学で、薬を自然界から入手する以外に方法がなかった時代に、自然界で何が薬として利用できるのかを研究する学問である。奈良時代以前に中国から伝えられたとされ、当初は中国の本 ...
-

-
豊後府内に住み、沈堕の滝を描いた雪舟
2021/7/6
雪舟等楊(1420-1506)の前半生については不明な点が多く、若いころに京都に出て相国寺の春林周藤に禅を学び、僧としての修業のかたわら、如拙や周文の画を学んだとされる。はっきりしてくるのは40代にな ...
-
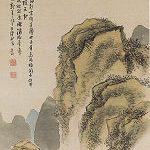
-
日田の三絶僧・平野五岳
2021/7/6
日田専念寺の僧・平野五岳(1811-1893)は、詩、書、画三分野すべてに傑出しているとして「三絶僧」と称された。詩は白楽天に私淑し、書を独学、画は田能村竹田の画法を研究した。画に関しては、田能村竹田 ...
-
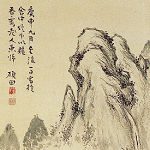
-
竹田門の四天王のひとりに数えられた博学者・後藤碩田
2021/7/6
後藤碩田(1805-1882)の生家は乙海村(現在の大分市鶴崎)にあり、酒造、煙草や穀物売買などを手広く行なっていた豪商で、碩田の父・守只は、家業に励むかたわら、華道や茶道などの文化面にも高い関心を示 ...
-

-
南画の復興と後進の指導に尽力した田能村直入
2021/7/6
田能村直入(1814-1907)の叔父・渡辺蓬島は田能村竹田の初期の師のひとりということもあり、直入は幼いころから画に強い興味を示していて、9歳で竹田に師事した。竹田はその画才を愛し、直入は養子となり ...
-

-
最も正しく田能村竹田の系譜を受け継いだ門人・帆足杏雨
2021/7/6
帆足杏雨(1810-1884)は、最も正しく田能村竹田の系譜を受け継いだ門人とされるが、その一方で、中国画学習を深め、自己の画技を進めていくなかで、独自の画風を確立した。天保9年以降はほとんど大分を離 ...
-
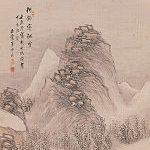
-
竹田門下の夭折の鬼才・高橋草坪
2021/7/6
田能村竹田が画才を認め、最も期待していた門人は、杵築の高橋草坪(1804-1835)とされる。いかに竹田が草坪の画才を認めていたかは、自著『竹田荘師友画録』に門人のなかで唯ひとり取り上げられていること ...
-
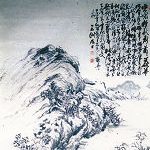
-
近世日本最大規模の私塾・咸宜園を開いた日田の広瀬淡窓
2021/7/6
日田豆田魚町の商家に生まれた広瀬淡窓は、幼いころから漢学・漢詩を学び、24歳の時に家督を弟に譲り、寺の学寮を借りて塾を開いた。塾は移転し、名を「成章舎」「桂林園」と変え、文化14年には、叔父・月化の隠 ...
-
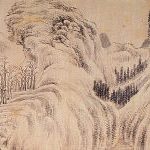
-
耶馬溪の名付け親・頼山陽と豊前中津青村の曽木墨荘
2021/7/6
田能村竹田が生涯もっとも親しく交遊したのが頼山陽(1781-1832)である。山陽は日本外史を著したことで知られる漢詩人で、大坂で生まれ広島で育ったが、その後、居を京都に定め、多くの文人・画人と交流し ...
-

-
田能村竹田と豊後杵築ゆかりの儒者・篠崎小竹
2021/7/6
篠崎小竹(1781-1851)は、近世後期の大坂を代表する文人で、漢詩、漢文に優れ、書家としても高名である。父親が豊後杵築の出身ということもあり、田能村竹田とは京坂の文人グループで親しく交遊し、よく遊 ...
-
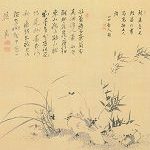
-
田能村竹田と豊前中津の雲華上人
2021/7/6
雲華上人(1773-1850)は、姓を末広(弘)といい、豊前国中津の正行寺第十六世住職をつとめた僧である。江戸後期の東本願寺教学の最高学職である講師をつとめ全国を遊説する一方で、田能村竹田(1777- ...