-
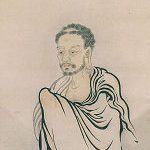
-
佐土原藩の絵師・狩野永諄
2021/7/6
佐土原藩では狩野永諄(1652-不明)が絵師としてつとめた。永諄は佐土原藩の家臣ではなく、絵師として招かれて佐土原に来た人物と思われる。作品は、佐土原町の大光寺に残っている「出山仙」「維摩居士図」など ...
-
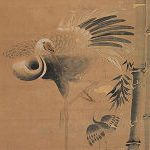
-
高鍋藩御用絵師を代々世襲した安田家
2021/7/6
高鍋藩では、安田義成(不明-1696)を初代とする安田家が、代々世襲で御用絵師をつとめた。初代義成は、木挽町狩野家の狩野尚信の門人だったが、高鍋藩二代藩主・秋月種春に招かれて寛文7年に高鍋にきた。それ ...
-
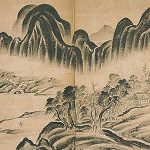
-
都城における江戸期最後の狩野派・中原南渓
2021/7/6
中原南渓(1830-1897)は、都城領主・島津久静の命により、鹿児島の狩野派・能勢一清に師事し狩野派の画法を学んだ。長峰探隠以来の名手とされ、久静のお抱え絵師となり、狩野派らしい筆法で多くの名作を世 ...
-

-
鍛冶橋狩野派に学んだ山路探定と長峰探隠
2021/7/6
18世紀初めまでは、都城に数多くの絵師の名前が残っているが、18世紀中頃から19世紀前半の間に名前が見られるのは、山路探定(1728-1793)と長峰探隠(1785-1861)の二人だけであり、ともに ...
-

-
狩野常信門下の四天王のひとり・永井慶竺
2021/7/6
都城には竹之下信成と同時代の絵師として永井実益(1637-1696)がいた。系図によると実益の父・利挙は二度結婚しており、一人は能賢の弟子・湛慶の娘で、もう一人は白谷卜斎の娘であり、実益は白谷卜斎の縁 ...
-

-
木挽町狩野家に学んだ都城の絵師・竹之下信成
2021/7/6
都城島津家の絵師たちは、ほとんど狩野派に学んでいるが、白谷卜斎にやや遅れて出た内藤等甫(不明-1664)、竹之下信成(1639-1682)、津曲朴栄(1654-1701)は木挽町狩野家に学んでいる。等 ...
-
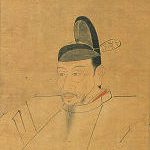
-
都城島津家の最初の絵師・白谷卜斎
2021/7/6
宮崎の美術の中で、まず最初に狩野派の絵師として登場するのが、都城藩の白谷卜斎(不明-1658)である。白谷卜斎は都城領主・北郷忠能に仕え、文録の頃、京都に出て狩野宗家に学んだ。卜斎の作品「豊太閣図」は ...
-

-
異色の抽象画家・荒井龍男と昭和期の大分県の洋画家
2024/4/10
昭和に入ると、それまで官展中心だった大分県出身の洋画家のなかでも、在野団体で個性的な作品を発表し、名をなす者が出てきた。荒井龍男(1904-1955)は中津市に生まれ、幼くして家族とともに朝鮮に渡り、 ...
-

-
片多徳郎と西ヶ原グループ
2021/7/6
明治40年に開設された文展に大分県出身の洋画家として初めて入選したのは豊後高田市出身の片多徳郎(1889-1934)だった。片多は、東京美術学校在学中の明治42年、第3回文展に「夜の自画像」が初入選し ...
-

-
消えた近代日本洋画の開拓者・藤雅三
2021/7/6
この作品は、米国ネブラスカ州オマハのジョスリン美術館に所蔵されていたもので、来歴などの問い合わせを受けた愛知県美術館の高橋秀治美術課長(当時)の調査により、平成20年(2008)、藤雅三の作品であるこ ...
-

-
吉田四代の祖・吉田嘉三郎と不同舎で学んだ大分出身の洋画家
2021/7/6
中津市出身の吉田嘉三郎(1861-1894)は、彰技堂で洋画を学び、日本初の洋画美術団体・明治美術会の通常会員となるなど、活躍が期待されたが、33歳で没した。しかし、嘉三郎が福岡県立中学修猷館で教員を ...
-

-
東京の画塾で学んだ大分の初期洋画家
2021/7/6
沈堕の滝は、雪舟も描いている豊後大野市にある名瀑で、諫山は大分県令(知事)・香川真一の依頼によりこの滝を描き、明治10年の県勧業博覧会に出品しているが、現在は残っていない。この作品は、その時の写生をも ...
-
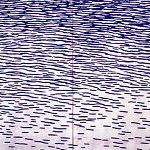
-
福田平八郎の登場、そして高山辰雄へと続く大分出身の日本画家
2024/12/16
大分県の近代日本画史の上に占める福田平八郎の存在は大きい。大分県では明治末期まで幅広い南画の展開がみられ、明治30年代における新日本画運動も弱々しいものだったが、平八郎の登場により、大分画壇はにわかに ...
-

-
京都の大分県画壇の草分け・高倉観崖と牧皎堂
2021/7/6
福田平八郎が画壇で注目を受ける以前に、京都で活躍した大分県出身の日本画家として、高倉観崖と牧皎堂がいる。彼らは京都での大分県画壇の草分けともいえる存在で、大分県内で藤原竹郷や松本古村らが興した近代日本 ...
-
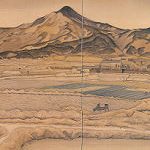
-
福田平八郎の師から弟子になった首藤雨郊
2021/7/6
近代日本画の大家・福田平八郎(1892-1974)の才能をいち早く見出し、絵画の道に導いたのは、当時小学校の教諭をしていた首藤雨郊(1883-1943)である。首藤は、大分県師範学校を卒業後、大分師範 ...
-

-
大分県に近代日本画を持ち込んだ藤原竹郷と松本古村
2021/7/6
南画でなければ日本画ではないという空気の強かった南画王国・大分県に、新しい日本画を持ち込み、美術教師として県内に広めた最初の人物は、東国東郡出身の藤原竹郷(1872-1963)とされる。藤原は、明治3 ...