-

-
三熊派の伝統を守って桜の花を描き続けた織田瑟々
2023/7/31
織田瑟々(1779-1832)は、近江国神崎郡御園村川合寺(現在の東近江市川合寺)に、津田貞秀の長女として生まれた。津田家の先祖は織田信長の九男信貞にはじまり、豊臣秀吉の時に神崎郡内の御園荘に領地をも ...
-

-
名古屋にいち早く写実的な描写を伝えた張月樵
2023/7/28
張月樵(1765or1772-1832)は、彦根城下の表具師・総兵衛の子として生まれた。幼いころから画を好み、同郷の市川君圭に学び、その後京都に出て与謝蕪村門下の松村月渓に師事し、師の号から一字とって ...
-
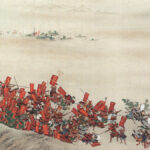
-
湖北・長浜に京都の文化的香りを伝えた山縣岐鳳
2023/7/26
山縣岐鳳(1776-1847)は、京狩野の画人・山縣頼章の子として京都に生まれた。父の頼章は伏見宮家の邦頼親王に仕えていたが、天明8年の天明の大火を機に一家で京都から長浜に移住した。岐鳳は長浜で父に画 ...
-

-
放浪に生きたもうひとりの近江蕪村・横井金谷
2023/7/24
放浪の画人で「近江蕪村」と称された浄土宗の僧・横井金谷(1761-1832)の生涯を知るうえで参考になるのが、金谷が自ら著した『金谷上人御一代記』である。同書は、挿画入りで面白おかしくつづられており、 ...
-

-
与謝蕪村に師事し「近江蕪村」と称された紀楳亭
2023/7/21
大津で「九老さん」と親しみを込めて呼ばれている画人・紀楳亭(1734-1810)は、山城の鳥羽に生まれ、与謝蕪村に画と俳諧を学んで京都で活動していたが、天明8年の天明の大火を機に、蕪村門下で同門だった ...
-

-
伊藤若冲の贋作を制作して名声を失った市川君圭
2023/7/19
市川君圭(1736-1803)は、坂田郡醒井村大字醒井(現在の米原市)に生まれた。醒井は中山道の宿場があった宿場町で、加茂神社境内から湧き出る名水「居醒の清水」でも知られている。 君圭が誰に画を学んだ ...
-

-
高田敬輔に学び風俗画家として大成した月岡雪鼎
2024/12/11
月岡雪鼎(1710-1787)は、滋賀県蒲生郡大谷村(現在の日野町大谷)に生まれた。本姓は木田といい、号は信天翁、露仁斎などたくさんあるが、雪鼎がもっとも知られている。姓の「月岡」も最初は号で、故郷の ...
-

-
近江日野の信楽院に多くの作品を残した高田敬輔
2024/11/13
高田敬輔(1674-1755)は、近江日野(現在の滋賀県蒲生郡日野大窪町杉野神)に生まれた。祖先は藤原氏の出自で、永禄年間に高田姓となり、織田信長に従って尾張にいたが、敬輔の曽祖父の代になって近江日野 ...
-
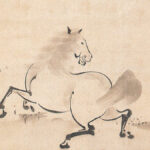
-
14代にわたり彦根藩主をつとめた井伊家の画人
2023/7/12
井伊家は、初代直政から最後となった17代藩主直憲まで14代にわたり彦根藩主をつとめたが、そのなかで画を嗜み、作品を残している藩主としては、6代藩主直恒、9代藩主直惟、13代藩主直幸(英)がいる。確認で ...
-

-
六芸に通じた才人で蕉門十哲に数えられた森川許六
2023/7/10
江戸時代の早い時期に活躍した彦根の画人としては、森川許六(1656-1715)がいる。許六は彦根藩士の子として彦根城下に生まれ、若いころから漢詩を学び、画は江戸の中橋狩野家の狩野安信に学んだとされる。 ...
-

-
近世初期風俗画を代表する傑作・彦根屏風
2023/7/7
「彦根屏風」は、代々彦根藩主だった井伊家に伝来したことからこの名がある。江戸時代の寛永年間(1624-1644)の制作と考えられており、注文主は明らかになっていないが、江戸時代後期に井伊家が入手したこ ...
-

-
京狩野の祖・狩野山楽
2026/2/2
狩野山楽(1559-1635)は、近江浅井家の家臣の子として近江国蒲郡に生まれた。父の木村永光は、浅井長政、豊臣秀吉に仕えた武人で、余技で狩野元信に画を学んだという。山楽は15歳の時に父の縁故で秀吉の ...
-

-
湖国が生んだ桃山時代を代表する武人画家・海北友松
2023/7/3
海北友松(1533-1615)は、近江国(現在の滋賀県)坂田郡の武士の家に生まれた。父の海北綱親は近江浅井家の重臣六家の一人で、浅井長政の祖父・亮政以来「家中第一の剛の者」とうたわれた猛者で、浅井長政 ...
-

-
一貫して「松」を作画活動の中心においた新道繁
2023/6/26
新道繁(1907-1981)は、福井県板井郡(現在の坂井市)に生まれた。東京府工芸学校在学中から水彩画に親しみ、大正14年の第6回帝展で初入選し、その後も帝展、新文展に出品した。また、光風会にも出品し ...
-

-
昭和初期のプロレタリア美術運動の流れのなかで労働者を描いて高い評価を得た堀田清治
2023/6/23
堀田清治(1898-1984)は、福井市に生まれ、中学卒業後に上京し、太平洋美術研究所で高間惣七に師事した。大正13年の第1回展から槐樹社に出品し、昭和6年に同会が解散するまで出品し、槐樹社賞を3回受 ...
-

-
大正期新興美術運動の中心人物として活動したが、三科展瓦解後は絵画制作から離れた木下秀一郎
2023/6/21
木下秀一郎(1896-1991)は、日本医学専門学校(現在の日本医科大学)で医学を学んでいたが、在学中から絵画制作を行い、大正9年に結成された大正期新興美術運動の始まりとされる「未来派美術協会」の第1 ...