-

-
大阪洋画壇の草分け的存在・山内愚僊
2025/4/14
大阪洋画の草創期に活躍した画家としては、浮世絵の月岡芳年門下の鈴木蕾斎(不明-不明)が知られるが、本格的に大阪で洋画がはじまるのは、山内愚僊、松原三五郎が相次いで大阪に移り住んでからといえる。 山内愚 ...
-

-
森派の森一鳳に「円山風」を学んだ森関山
2025/4/11
江戸時代の大坂画壇において重要な流派のひとつである森派は、もともと狩野派風を描いていた森陽信、周峰、祖仙(のちに狙仙に改号)の三兄弟のうち、写生画の作風を確立した狙仙にはじまるとされる。狙仙は画題をほ ...
-

-
狩野派と円山派を折衷した画風を確立した渡辺祥益
2025/4/9
渡辺祥益(1848-1905)は、渡辺梁益の二男として大坂に生まれた。父の梁益は、京狩野家9代の狩野永岳に学び、禁裏御用をつとめたという。祥益は、父の没後慶応3年に京都に出て狩野永祥について4年間学ん ...
-

-
動物の生態を研究し写生につとめた望月金鳳
2025/4/7
望月金鳳(1846-1915)は、大坂平野町に接骨医・平野浄恵の二男として生まれた。9歳の頃林仁鳳に円山派の手ほどきを受け「芳林」と号し、その後四条派の西山芳園・完瑛に学び「金鳳」と号した。17歳の時 ...
-

-
古き浪速の名勝地を描き人気を博した久保田桃水
2025/4/4
久保田桃水(1841-1911)は、京都に生まれ、四条派の横山清暉に学び、清暉没後は19歳で大阪に移り西山芳園に師事した。明治20年に上京し皇居千種間の欄間や芝離宮洋館の天井画を手掛け、一方で内外各種 ...
-

-
西山完瑛に学んだ武部秋畦・白鳳兄弟
2025/4/2
武部秋畦(1868-1906)、武部白鳳(1871-1927)の兄弟は、歌川派の浮世絵師の流れを汲む画家・武部芳峰の子として大阪に生まれ、兄弟で西山完瑛(参考)の門に学んだ。兄の秋畦は、朝日新聞社で挿 ...
-

-
船場派を率いる先達の役割を果たした西山完瑛
2025/3/31
西山完瑛(1834-1897)は、四条派の西山芳園の子として江戸後期の大坂に生まれた。父の芳園は、大坂に四条派を流行らせたとされる画家で、完瑛もその伝統を受け継ぎ、温雅で洒脱な人物花鳥を得意とし、西山 ...
-

-
平井直水、大塚春嶺ら深田直城の門人
2025/3/28
平井直水(1860-不明)は、30歳で画家を志し深田直城に師事した。孔雀を描くのを得意とし、日本絵画協会などで受賞を重ね、明治40年に日本初の官展として開設された文展の第1回展では大阪唯一の入選者とな ...
-
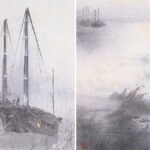
-
大阪四条派の重鎮として後進を育成した深田直城
2025/3/26
深田直城(1861-1947)は、近江国の膳所藩士の家に生まれた。8歳の時に京都に出て絵画を習いはじめ、14歳で父の友人である加島菱洲に洋画を学び、翌年森川曽文に師事して四条派の写生画法を学んだ。18 ...
-

-
終生「船場の絵描き」として生きた庭山耕園
2025/3/24
庭山耕園(1869-1942)は、現在の兵庫県姫路市に生まれた。庭山家は代々姫路藩の酒井家に仕えており、父は大坂の蔵屋敷の仕事に携わっていたが、明治初年の廃藩で職を失ったため家族で大阪北船場に転居した ...
-

-
写生的な作風で「精細麗艶」といわれた上田耕冲
2025/3/21
上田耕冲(1819-1911)は、円山応挙門下の上田耕夫の子として京都に生まれた。父に画を学び、父とともに大坂に移ったが、その後死別したため豪商・平野屋五兵衛の援助で長山孔寅に学んだと伝わっている。一 ...
-

-
赤松雲嶺、塚口竹香、川本月香ら姫島竹外の門人
2025/3/19
姫島竹外に学んだ南画家としては、竹外門下の双璧とされた山田秋坪、水田竹圃をはじめ、赤松雲嶺、塚口竹香、川本月香、幸松春浦、安田半圃、泥谷文景、姫島竹亭らがいる。 赤松雲嶺(1892-1958)は、8歳 ...
-
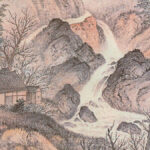
-
姫島竹外門下で山田秋坪とともに双璧とされた水田竹圃
2025/3/17
水田竹圃(1883-1958)は、大阪に生まれ、姫島竹外の門に入り南画を学び、竹外門下では山田秋坪とともに双璧とされた。明治45年に中国を巡遊し、帰国後名声を高めたという。大正元年の第6回文展で初入選 ...
-

-
姫島竹外に学び花鳥画を得意とした山田秋坪
2025/3/14
山田秋坪(1877-1960)は、豊前国の中津藩士の家に生まれ、幼くして大阪に転居した。父の秋溪(秋佳)に南画と漢学を学び、父の没後は姫島竹外に師事した。日本青年絵画協会展や内国勧業博覧会で受賞を重ね ...
-
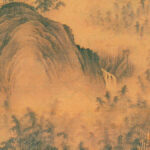
-
近代大阪南画壇の重鎮として活躍した姫島竹外
2025/3/12
姫島竹外(1840-1928)は、筑前国の福岡藩士で代官をしていた姫島家の長男として生まれ、父に二天流の剣法を教わり、藩校・修猷館で学んだ。また画を好み、はじめ村田東圃に学び、のちに石丸春牛に師事した ...
-

-
南画のほか銅版画も手掛け地図や刊行物を残した森琴石
2025/3/10
森琴石(1843-1921)は、摂津国有馬郡湯元(現在の兵庫県神戸市北区有馬町)の梶家に生まれ、3歳の時に大坂の森家の養子となった。鼎金城に師事して南画を学び、のちに忍頂寺静村にもついた。また、高木退 ...