-

-
長府藩の粋な御用絵師・度会文流斎と笹山家
2021/7/9
近世の周防・長門国では、強固な流派体制を誇った雲谷派が幕末まで続いたが、狩野派も各藩で御用絵師をつとめ、多くの絵師を輩出している。長府藩においては、狩野芳崖の父である狩野晴皐、のちに明治の教育者として ...
-

-
雪舟の後継者・雲谷派の系譜
2026/2/16
雲谷派のはじまりは、長州藩を治めていた毛利輝元が、原治兵衛直治(のちの雲谷等顔)に雪舟のアトリエだった雲谷庵と雪舟筆「山水長巻」を与え、雪舟流の正統を継ぐように命じたことに起因する。等顔は狩野派を学ん ...
-

-
靉光と戦前の広島の洋画家
2021/7/9
美術文化協会の設立に参加し、昭和10年代の前衛運動を担った靉光(1907-1946)は、戦時下に体制に順応していった美術文化協会を離れ、新しい活動の場として新人画会を結成したが、翌年には召集を受け、終 ...
-

-
広島洋画の先駆者・小林千古
2024/12/14
広島に初めて本格的な洋画をもたらした人物として小林千古(1870-1911)があげられる。千古は、出稼ぎ労働者として渡米し、苦学してサンフランシスコの美術学校を卒業、さらにヨーロッパにも遊学し、黒田清 ...
-

-
近・現代の中央画壇に大きな影響を与えた広島出身の日本画家
2025/3/27
大正・昭和期になると中央画壇で独自の活動をする広島出身の日本画家が出てくる。高田郡生まれの児玉希望(1898-1971)は、写実に基礎をおきつつ、古画や洋画の手法も取り入れ多様な作品を発表、広島で日本 ...
-

-
広島四条派の系譜、明治・大正期に広島画壇を牽引した里見雲嶺
2025/3/27
江戸後期の山田雪塘から始まる広島の四条派は、雪塘の門人である山県二承、さらに二承の門人・里見雲嶺(1849-1928)と続き、雲嶺は明治・大正期における広島画壇の中心的な画家として活躍した。雲嶺の画法 ...
-

-
菅茶山・頼山陽の広島の門人
2021/7/9
福山が誇る儒学の大成者・菅茶山は、京坂地方や江戸で与謝蕪村、池大雅ら多くの著名文人と交友し風雅の道を究めたが、その生涯の大半を郷土の神辺で過ごし、私塾などを通して地元の教育に尽力した。また、京都で名を ...
-

-
菅茶山と頼山陽
2021/7/9
江戸後期、広島地方からは2人の著名な儒者が出ている。当代随一の漢詩人と称され、郷土の教育に尽力した菅茶山(1748-1828)と、文化文政期の京都でサロン的に発生した文化人グループの中心人物として活躍 ...
-
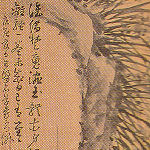
-
広島の南画家
2021/7/9
広島の南画家としては、紀伊国に生まれ京都で小田海僊に学び、幕末から明治にかけて安芸・備後地方を巡り、晩年は広島で絵画の指導をした名草逸峰(1821-1889)、陸奥国に生まれ、狩野派の菅原晋斎に学んだ ...
-

-
福原五岳と尾道の画人
2025/3/27
京都で池大雅に学び、大坂で多くの門人を育て画壇に大きな影響を及ぼした南画家・福原五岳(1730-1799)は、生まれ故郷である尾道にしばしば帰郷し、絵画の指導にあたった。尾道の豪商・福岡屋の平田五峯( ...
-

-
広島の南蘋派・岡岷山
2021/7/9
江戸中期広島の代表的絵師として知られる岡岷山(1734-1806)は、はじめ狩野派の勝田友溪に手ほどきを受け、のちに南蘋派の名手とされる宋紫石に学び影響を受けた。岷山は藩の御用絵師として領内各地を観察 ...
-

-
福山藩の住吉派・村片相覧と藩主・阿部正精
2021/7/9
福山藩主の阿部氏は代々、学問、文芸、芸術などを積極的に奨励し、藩主自らも風雅を好み、画を描いた。なかでも三代阿部正右(1724-1769)、四代阿部正倫(1745-1805)、五代阿部正精(1774- ...
-

-
福山藩を代表する円山四条派の画人・藤井松林と門人
2021/7/9
藤井松林(1824-1894)は、福山藩士の子として福山城下長者町に生まれ、幼ないころから画才を発揮、14歳で福山藩から絵師の加勢を仰せ付けられ、高田杏塢や吉田東里に画の手ほどきを受けた。のちに京都に ...
-

-
四条派を学んだ杉野怡雲ら福山藩士
2021/7/9
福山藩では藩士のなかに四条派を学んだものが多い。杉野怡雲(1791-1865)は家督を弟に譲り、京都に出て松村呉春、岡本豊彦に学んだ。帰郷後は城北丘上に住み、藩士・町人を問わず交遊し、詩酒や茶席がある ...
-

-
広島藩の四条派・山田雪塘と門人
2021/7/9
広島藩の四条派としては、広島白島町に住んでいた町絵師・山田雪塘(不明-不明)が、松村呉春に学び、頼杏坪、菅茶山、飯田篤老ら多くの儒者や文人と交わり、彼らの讃のある作品を残している。山田雪塘の門人として ...
-
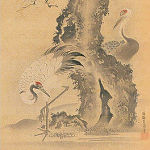
-
福山藩の狩野派、片山墨随斎守春・索準斎守規父子
2021/7/24
幕府御用絵師の狩野派は、福山藩にも早くからもたらされ、明和・天明の頃に土屋索進斎(不明-不明)が出ている。索進斎は、福山城下深津町鉄屋に生まれ、京都に出て狩野派の鶴沢探鯨・探索に学び、法橋に叙せられた ...