-

-
父・永徳とは対照的な優美な作風を示した狩野光信
2026/1/14
狩野光信(1561or1565-1608)は、狩野永徳の長男として京都に生まれた。生年には異説もあるが、永禄8年(1565)生まれだとすると、12歳の時に父とともに安土城の障壁画制作に携わり、17歳の ...
-

-
兄・永徳のもと狩野宗家を守った狩野宗秀
2026/1/12
狩野宗秀(1551-1601)は、狩野永徳の8歳下の弟で、兄から画法を学んだ。兄・永徳の影響力は絶大だったとみえ、掲載の「花鳥図屏風」など永徳作品によく似た大画作品を残している。永徳の弟には宗秀のほか ...
-

-
活気あふれる芳醇な桃山美術を演出した狩野永徳
2026/1/9
狩野永徳(1543-1590)は、狩野松栄の長男として生まれ、若くして狩野宗家を継承した。幼いころから将来を嘱望され、祖父・元信のもと徹底的な英才教育がなされたと思われ、さまざまな逸話から元信の孫・永 ...
-

-
桃山期の狩野派を隆盛に導いた陰の功労者・狩野松栄
2026/1/7
永禄2年、狩野派発展のために尽力し続けた狩野元信が83歳で没し、その家督は三男の松栄が継いだ。その時点ですでに長男の宗信は没していたが、二男の秀頼は健在で、さらに養子先から狩野家に戻ってきていたと思わ ...
-

-
桃山期に流行する近世初期風俗画の先駆者・狩野秀頼
2026/1/5
狩野秀頼(不明-不明)は、狩野元信の二男で、若くして東寺の仏画制作を家業としていた本郷家に養子に入った。10数年ほど東寺で大絵師職をつとめていたが、突如として本郷家から狩野家に戻っており、狩野宗家を継 ...
-

-
父元信に先んじて没した長男の狩野宗信
2025/12/26
狩野宗信(不明-1545)は、江戸時代の画譜類によると狩野元信の長男で、父よりかなり早く没したとされるが、その伝歴については不明な点が多い。没年に関しては『言継卿記』天文14年(1545)4月14日条 ...
-

-
元信様式を摂取した跡がみられる狩野雅楽助
2025/12/24
狩野雅楽助(1513-1575)は、古くから狩野元信の弟とみなされていたが、近年になって元信の子とする説も提示されており、いまだに確証は得られていない。ただその画風には元信の画法を忠実に学んだところが ...
-
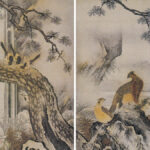
-
狩野派繁栄の基礎を確立した狩野元信
2025/12/22
狩野元信(1476-1559)は、狩野派初代・狩野正信の長男として京都に生まれ、はじめ父に画法を学び、さらに宋元画人のさまざまな筆法を研究し、父譲りの堅固な構成力を基に、元信様式ともいうべき明快で端正 ...
-

-
狩野派の始祖・狩野正信
2025/12/19
狩野派の始祖・狩野正信(1434?-1530?)の出自については、曖昧な点も多いが、伊豆(静岡県)の出身と思われ、その後京都に出たとされる。歴史上初めて登場するのは、寛正4年の相国寺雲頂院の壁画制作だ ...
-

-
古典回帰を思わせる濃麗な彩色を身上とした土佐光茂
2025/12/17
土佐光信の後継者・土佐光茂(1496?-不明)は、戦国期の画壇において独自の画風に到達し、父光信とは異なる古典回帰を思わせる濃麗な彩色を身上とした。光茂の描いた作品は近世以降のやまと絵の図様として多く ...
-
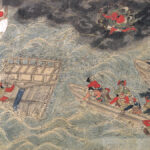
-
淡い彩色で土佐派に新風を吹き込んだ土佐光信
2025/12/15
土佐光信(1434?-1525?)は、土佐広周の嗣子で、土佐光弘の実子と思われる。光信に関する最も早い記録は、応仁の乱の直前、足利義政の室町邸における障子絵の制作に関するもので、その後、広周が後見役と ...
-

-
土佐派第四世代として長期にわたり活躍した土佐広周
2025/12/12
土佐派は15世紀前半に3つの工房に分岐し、土佐派第四世代の絵師としては、六角絵所の六角益継(不明-不明)、春日絵所の土佐光弘(不明-不明)、土佐行広の工房を継いだ土佐広周(不明-不明)の3名が主要な存 ...
-

-
南都東大寺「大仏縁起絵巻」を描いた芝琳賢
2025/12/10
奈良・東大寺に伝わる「大仏縁起絵巻」は、もともとあった20巻の絵巻を3巻に要約し直したもので、天文5年に成立した。内容は大仏を軸に展開し、詞書は上巻を後奈良上皇が、中巻を青蓮院尊鎮が、下巻を公順が担当 ...
-
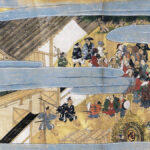
-
土佐派と異なる新奇な画風を示した掃部助久信・久国
2025/12/8
京都・西本願寺の「慕帰絵」は、観応2年に藤原隆章・隆昌父子の作画によって完成したのち、足利将軍家に貸し出されていたが、飛鳥井雅康のとりなしにより文明13年に京都・本願寺に返却された。ところが、全10巻 ...
-

-
京都本圀寺「日蓮聖人註画讃」を描いた窪田統泰
2025/12/5
京都・本圀寺に伝わる「日蓮聖人註画讃」は、日蓮聖人の生涯を描いた絵巻で、全5巻32段からなる。奥書や箱書によると、天文5年(1536)に日政の勧進によって若狭国遠敷郡(現在の福井県小浜市)の長源寺で制 ...
-
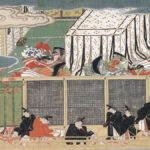
-
土佐派と唯一拮抗する活動を展開した粟田口隆光
2025/12/3
大阪・誉田八幡宮に伝わる「誉田宗廟縁起絵巻」は、永享5年(1433)、6代将軍・足利義教が奉納した絵巻で、全3巻に応神天皇の崩御・葬送と陵墓建設、欽明天皇の勅定により山陵のかたわらに宝殿を建立し八幡大 ...