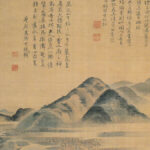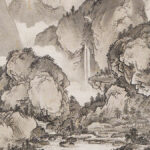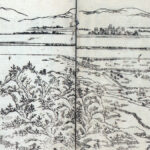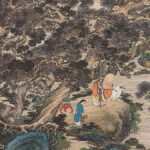上田耕冲「箕面山真景図」逸翁美術館蔵
上田耕冲(1819-1911)は、円山応挙門下の上田耕夫の子として京都に生まれた。父に画を学び、父とともに大坂に移ったが、その後死別したため豪商・平野屋五兵衛の援助で長山孔寅に学んだと伝わっている。一説には孔寅は師となることを拒み、仲間として扱ったという。
その写生的な作風は「精細麗艶」といわれ、遊歴を好み、山水花鳥を得意とした。明治維新後は、混乱のなか蝙蝠傘に絵を描くなどして糊口をしのぎ、明治17年に樋口三郎兵衛が設立した私立浪華画学校の教員となった。子の耕甫や庭山耕園ら後進を育て、大阪天満宮の梅花殿に、門下のものとともに多くの作品が伝わっている。
子の上田耕甫(1860-1944)は、父に画を学び、円山四条派の風景画や人物画を描くとともに、金屏風に草花を濃厚な色彩で描いた琳派風の作品も手掛けた。父と同様に茶碗や棗などの茶道具への絵付けも行ない、茶道と深くかかわった。住友家、藤田家、野村家などの財界人と交流し、藤田家の能舞台も描いたという。
上田耕冲(1819-1911)うえだ・こうちゅう
文政2年京都生まれ。上田耕夫の子。名は及、字は頼方、通称は万次郎。父とともに大坂に移ったが天保2年に父が没したため、画を四条派の長山孔寅に学んだと伝わっている。「精細麗艶」といわれた四条派風の写生的な作風で、山水図や花鳥図を得意とした。各地を遊歴し、柁木町または過書町で暮らした。明治17年道修町に設立された私立浪華画学校の教壇に立ち、門下生に庭山耕園がいた。明治21年大阪府立博物場内に建てられた美術館の天井壁画を描いた。明治23年第3回内国勧業博覧会、明治28年第4回内国勧業博覧会に出品。生年に関しては文政3年説もある。明治44年、93歳で死去した。
上田耕甫(1860-1944)うえだ・こうほ
万延元年大坂生まれ。上田耕冲の子。祖父は上田耕夫。名は長、字は頼通、通称は市朗。別号に橙園主人、停雲、圓萬堂などがある。父に18歳から画を学んだ。明治15年第1回内国絵画共進会出品。明治21年大阪府立博物場内美術館の天井壁画の制作に父の助手として参画。明治23年第3回内国勧業博覧会出品。表具師・井口古今堂の三代目邨僊の推薦を受けて明治44年より住友家15代春翠の長女に日本画を教えた。また、同家須磨別邸での招待会や海外からの来賓があった際に、村田香谷、望月玉溪らとともに席上揮毫を行なった。昭和10年代後半に神戸に転居するまで大阪に暮らした。昭和19年、84歳で死去した。
大阪(90)-画人伝・INDEX
文献:絵草紙に見る近世大坂の画家、近世大阪画壇、大阪人物誌巻4、サロン!雅と俗:京の大家と知られざる大坂画壇、上島鳳山と大阪の画家たち、大阪ゆかりの日本画家、近世の大阪画人