-

-
洋風画にも通じた唐絵目利・石崎融思と長崎の洋風画家
2021/7/6
長崎に入ってきた絵画の制作年代や真贋などを判定、さらにその画法を修得することを主な職務とした唐絵目利は、渡辺家、石崎家、広渡家の3家が世襲制でその職務についていた。享保19年には荒木家が加わり4家とな ...
-

-
長崎洋風画の先駆者・若杉五十八と荒木如元
2021/7/11
キリスト教の禁止令とともに、西洋画もその弾圧の対象とされ、さまざまな制約が加えられるようになった。唯一の開港地だった長崎では、西洋や中国の文化が流入する得意な環境のもと、オランダ人やオランダ船などの西 ...
-

-
南蘋派の開祖・熊斐と南蘋派の画人
2022/3/4
南蘋派は、清から渡来した沈南蘋によって伝えられた画風で、緻密な写生と鮮やかな彩色が特徴である。沈南蘋は、享保16年に渡来して18年まで長崎に滞在しており、この間に、中国語の通訳である唐通事をしていた熊 ...
-

-
唐絵目利広渡家の画系
2021/7/18
唐絵目利四家のひとつである広渡家は、武雄鍋島藩で御用絵師をつとめていた初代広渡心海に学んだ広渡一湖(1644-1702)に始まる。一湖は熊本の生まれだが、24歳で長崎に移り住み、心海が一時長崎に滞在し ...
-

-
唐絵目利石崎家初代・石崎元徳らを輩出した小原慶山の画系
2021/7/6
初期の長崎画壇に大きな影響をあたえた小原慶山(不明-1733)は、丹波に生まれ、京都を経て江戸に出て狩野洞雲に学んだ。その後、長崎に移り住み河村若芝に師事した。作品には雪舟派や狩野派の筆致がみられ、唐 ...
-

-
長崎唐絵の奇才・河村若芝とその画系
2021/7/6
渡辺鶴洲と並び、逸然性融門下の双璧と謳われた河村若芝(1630-1707)は、師の奇狂な造形美をさらに増幅させた画風で、長崎唐絵の代表的な奇才と称されている。若芝は、肥前佐賀の豪族の出身で、故あって長 ...
-

-
続長崎画人伝を記した鶴洲の高弟・荒木千洲とその画系
2021/7/6
長崎画人伝によって唐絵目利の画系を後世に残す渡辺鶴洲の仕事は、その高弟である荒木千洲(1807-1876)によって引き継がれた。千洲が編纂した続長崎画人伝では、師の鶴洲およびその系統に属する人々、荒木 ...
-

-
長崎画人伝を著した唐絵目利渡辺家七代・渡辺鶴洲
2021/7/8
唐絵目利渡辺家7代を継いだ渡辺鶴洲(1778-1830)は、長崎画人伝の著者としても知られる。長崎画人伝は、一度途絶えたような形となった渡辺家を継いだ鶴洲が、唐絵目利の中での渡辺家の存在の挽回をはかる ...
-

-
唐絵目利の祖・渡辺秀石とその画系
2021/7/6
唐絵目利とは、長崎の地役人のひとつで、江戸時代唯一の開港地だった長崎に入ってきた絵画の制作年代や真贋などを鑑定、さらにその画法を習得することを主な業務とした。当初、絵目利と呼ばれていたが、元禄10年に ...
-
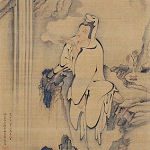
-
長崎漢画の祖・逸然性融
2021/7/6
隠元隆琦によって長崎に伝えられた黄檗宗には、黄檗肖像法によって肖像画を描いた喜多氏ら肖像画工のほか、興福寺の僧・逸然性融(1601-1668)を開祖とする漢画(唐絵)のグループがあった。漢画とは、江戸 ...
-
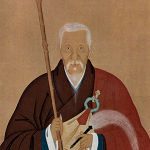
-
黄檗肖像画家・喜多元規とその画系
2021/7/6
17世紀中頃、黄檗宗の僧・隠元隆琦が渡来し、我が国に黄檗宗を伝えると、木庵性稲や即非如一、独立性易ら黄檗僧が続々と渡来し、長崎は黄檗文化の一大中心地となった。中国黄檗僧の渡来によって盛んになった黄檗宗 ...
-

-
南蛮美術と長崎の南蛮絵師
2021/7/6
天文12年、種子島に漂着したポルトガル人が日本に鉄砲を伝え、続く天文18年、イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルによってキリスト教が伝えられた。この時に来日したポルトガル人やスペイン人を総称して南蛮 ...
-

-
佐賀美術協会の創立と佐賀出身の画家たち
2021/7/12
大正2年、東京上野の茶屋に久米桂一郎、岡田三郎助ら佐賀県出身の画家が集まった。メンバーは久米、岡田のほかに、田雑五郎、山口亮一、御厨純一、北島浅一、さらに藤田遜ら東京美術学校の在学生たちも加わった。こ ...
-

-
北島浅一ら東京美術学校に学んだ佐賀の洋画家
2021/7/12
明治20年に東京美術学校が創設され、29年に西洋画科が新設されると、佐賀県の若者たちも上京して洋画を学ぶようになった。明治期に東京美術学校西洋画科に学んだ佐賀県出身の者としては、明治35年に入学した陣 ...
-
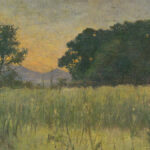
-
明治洋画壇で指導的役割を果たした久米桂一郎と岡田三郎助
2025/2/13
黒田清輝とともに日本洋画に外光派の画風を取り入れ、洋画団体白馬会を結成するなど、明治洋画壇で指導的役割を果たした久米桂一郎(1866-1934)は、佐賀城下に生まれ、8歳の時に家族とともに上京した。幼 ...
-

-
百武兼行によってはじまる佐賀洋画
2024/12/14
佐賀藩最後の藩主となった鍋島直大は、維新後は新政府の要職につくほか、明治4年には政府派遣の欧米視察団としてアメリカに渡り、その後はイギリスに留学した。その時に直大に随行したのが、御相手役として直大に仕 ...