-

-
多門や玉城と親しく交わり絵を学んだ丸田省吾
2024/12/14
都城に生まれた丸田省吾(1880-1961)は、従兄である山内多門(1878-1932)や、義兄にあたる益田玉城(1881-1955)と親しく交わり絵を学んだ画家である。省吾は従兄に多門を持つにもかか ...
-
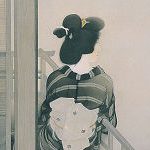
-
第9回文展の美人画室でデビューした都城の美人画家・益田玉城
2024/12/14
都城に生まれた益田玉城(1881-1955)は、15歳の時に京都に出て京都市美術工芸学校に入学したが、体を壊し休学して故郷に戻った。失意の玉城を励ましたのは同郷の山内多門(1878-1932)だと思わ ...
-
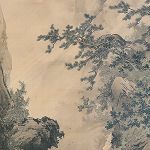
-
宮崎県を代表する日本画家・山内多門
2021/7/6
宮崎県を代表する日本画家に都城の山内多門(1878-1932)がいる。多門は、西南戦争の翌年である明治11年に都城市に生まれ、郷土の狩野派・中原南渓に画法を学んだ。その後、小学校の教師となるが、日本美 ...
-
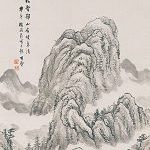
-
佐土原の南画家・根井南華
2021/7/6
根井南華(1883-1960)は、明治、大正、昭和にかけて活躍した佐土原の南画家である。南画の盛んな延岡から宮崎に移り住んでいた鈴木月谷に師事し、さらに佐藤小皐にも学んでいる。その作品や人物、画業につ ...
-

-
すぐれた書画を残した高鍋藩秋月家十一代・秋月種樹
2021/7/6
高鍋藩十代藩主・秋月種殷の弟でのちに養子となった秋月種樹は、幕末に外様大名としては異例の幕府若年寄となり、維新後は元老院議官や貴族院議員などをつとめた。その一方で、詩文、書画にすぐれ、風格ある書画を宮 ...
-

-
延岡の美人画家・奈須竹堂
2024/12/11
南画家がほとんどだった江戸後期から明治にかけての延岡で、一人異なるのが奈須竹堂である。竹堂は、若い頃に紋書修業のために京都に行き、修業中に三畠上龍に師事した。同門には豊後出身で、国東地方に京風美人画ブ ...
-

-
変わり者として知られた延岡の南画家・四屋延陵
2021/7/6
変わり者として知られた四屋延陵は、延岡藩の名門に生まれ、江戸で画を学び、その後は国内外を転々とした。彫刻にも巧みで、他人の家を訪れるとすぐにその家の盆に彫刻をする癖があったという。また、画に興じれば道 ...
-

-
近代延岡における南画家の第一人者・小泉二山
2021/7/6
江戸後期から南画が盛んに描かれるようになった延岡では、明治期になると小泉二山が出て人気を博し、近代延岡における南画家の第一人者と称された。二山は延岡で鈴木月谷に学んだのち、江戸に出て川上冬崖、田崎草雲 ...
-

-
延岡藩の南画家・岡部南圃
2021/7/6
延岡藩の最初の御用絵師・佐藤周鱗斎は狩野派だったが、その後の延岡の絵師は、周鱗斎の子の佐藤竹皐、孫の佐藤小皐をはじめ、そのほとんどが南画を学んでいる。延岡藩が南画王国だった豊後に近く、また飛び地もあっ ...
-

-
都城の四条派・赤池南鳳
2021/7/6
江戸後期になると、粉本主義に陥った狩野派は衰退していき、全国的に南画や写生主義の円山四条派がそれに代わっていった。都城でも四条派の絵が盛んに描かれるようになり、その先駆けである速見晴文をはじめ、鶏の絵 ...
-

-
延岡藩の御用絵師・佐藤周鱗斎
2021/7/6
経歴や作品が残っている延岡藩の御用絵師として、最も早い時期に名前が出てくるのは佐藤周鱗斎(1776-不明)である。周鱗斎の持ち物だった『狩野家累世所用画法』から狩野派の画を学んだことがわかるが、その習 ...
-

-
飫肥藩の絵師・狩野派の横山惟儀、養徳親子
2021/7/6
飫肥藩の絵師としては、天保の頃、横山惟儀(不明-不明)、横山養徳(1799-不明)の親子がいた。惟儀は江戸で狩野派に学び、「花木、禽鳥可ならざるはなし」と言われたという。早くから山林愛護の大切さを説い ...
-
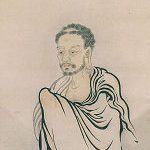
-
佐土原藩の絵師・狩野永諄
2021/7/6
佐土原藩では狩野永諄(1652-不明)が絵師としてつとめた。永諄は佐土原藩の家臣ではなく、絵師として招かれて佐土原に来た人物と思われる。作品は、佐土原町の大光寺に残っている「出山仙」「維摩居士図」など ...
-
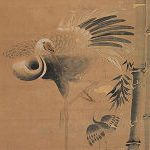
-
高鍋藩御用絵師を代々世襲した安田家
2021/7/6
高鍋藩では、安田義成(不明-1696)を初代とする安田家が、代々世襲で御用絵師をつとめた。初代義成は、木挽町狩野家の狩野尚信の門人だったが、高鍋藩二代藩主・秋月種春に招かれて寛文7年に高鍋にきた。それ ...
-
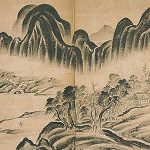
-
都城における江戸期最後の狩野派・中原南渓
2021/7/6
中原南渓(1830-1897)は、都城領主・島津久静の命により、鹿児島の狩野派・能勢一清に師事し狩野派の画法を学んだ。長峰探隠以来の名手とされ、久静のお抱え絵師となり、狩野派らしい筆法で多くの名作を世 ...
-

-
鍛冶橋狩野派に学んだ山路探定と長峰探隠
2021/7/6
18世紀初めまでは、都城に数多くの絵師の名前が残っているが、18世紀中頃から19世紀前半の間に名前が見られるのは、山路探定(1728-1793)と長峰探隠(1785-1861)の二人だけであり、ともに ...