-
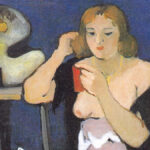
-
信濃橋洋画研究所で学び春陽展で活躍した秋口保波
2023/11/3
秋口保波(1897-1976)は、滋賀県犬上郡青波村(現在の彦根市芹川町)に生まれた。滋賀師範学校を出て教職につき、約10年間教員生活のかたわら絵画グループで研究し、のちに大阪の信濃橋洋画研究所に入り ...
-

-
黒田重太郎に学び関西の美術教育に尽くした伊庭伝治郎
2025/2/13
伊庭伝治郎(1901-1967)は、滋賀県野洲郡北里村(現在の近江八幡市)に生まれた。北里村小学校に通っていた時に父親が死去し、以後母と妹の3人暮らしとなった。高等科卒業後、近江八幡の呉服問屋森五商店 ...
-

-
信濃橋洋画研究所を設立し、関西を中心に後進の育成につとめた黒田重太郎
2023/10/30
黒田重太郎(1887-1970)は、滋賀県大津市に生まれ、幼少年期を大阪で過ごした。17歳の時に画家を志して京都の鹿子木孟郎(参考)に師事し、聖護院洋画研究所で浅井忠(参考)の指導も受けた。19歳の時 ...
-

-
大正期の京都洋画壇で活躍した国松桂渓
2025/2/13
国松桂渓(1884-1962)は、滋賀県栗太郎郡葉山村(現在の栗原町)に生まれた。中学校卒業後、京都に出て聖護院洋画研究所に入り浅井忠に師事し、その後、浅井忠を中心に創立された関西美術院に移った。浅井 ...
-

-
一貫して湖国風景を描き続けた岩本周煕
2023/10/24
岩本周熙(1900-1987)は、滋賀県高島郡剣熊村(現在の高島市)に生まれ、4歳頃に京都に移住した。大正13年に京都市立絵画専門学校を卒業し、その後は、同校の教授だった菊池契月に師事した。同門に草津 ...
-

-
京都紫野大徳寺瑞峯院に大画面の襖絵を残した野添平米
2023/10/18
野添平米(1895-1980)は、滋賀県栗太郎下笠村(現在の草津市下笠町)の農家に生まれた。18歳の時に画家を志して京都に出て菊池芳文の門に入り、芳文没後は芳文の娘婿にあたる菊池契月に師事した。 24 ...
-

-
官展を離れ孤高の宗教画家の道を歩んだ杉本哲郎
2023/10/16
杉本哲郎(1899-1985)は滋賀県大津市に生まれた。はじめ近隣に住んでいた日本画家の山田翠谷に画の手ほどきを受け、14歳の時に商業学校から京都市立工芸美術学校に転校したのを機に、山元春挙の私塾・早 ...
-
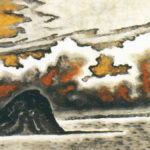
-
在野精神を貫くため新興美術院を創設した茨木杉風
2023/10/13
茨木杉風(1898-1976)は、滋賀県蒲生郡八幡町(現在の近江八幡市)の海産物問屋梅田屋の4代目・茨木芳蔵の長男として生まれた。5代目を継いで家業に従事しながら独学で画を学んでいたが、22歳の時に上 ...
-
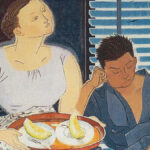
-
女性で最初の日本美術院同人となった小倉遊亀
2024/12/11
小倉遊亀(1895-2000)は、滋賀県滋賀郡大津丸屋町(現在の大津市中央1丁目)に生まれた。父親は大津で時計商を営んでいたが、遊亀が10歳の時、土木事業を興す野望を持ち、日露戦争終結後の満州に単身で ...
-

-
文展を離れ日本自由画壇の結成に参加した渡辺公観
2023/10/6
渡辺公観(1877-1938)は、大津鍵屋町(現在の大津市)に生まれた。父親は円満院門跡の侍医をつとめていた。円満院門跡は当時、大津における文化人の後援者的存在だったことから、公観も教養豊かな環境のな ...
-

-
滋賀県美術作家協会の初代理事長をつとめた疋田春湖
2023/10/4
疋田春湖(1891-1961)は、滋賀県膳所町(現在の大津市)に膳所藩士の子として生まれた。幼いころから画を好み、小学校卒業後、ちょうど京都から大津に移り住んでいた四条派の長谷川玉純について画を学び、 ...
-

-
春挙に学び師風とは異なる多様な作品を残した柴田晩葉
2023/10/2
柴田晩葉(1885~1942)は、滋賀県大津市新町に生まれた。父の孟教は、江戸の昌平坂学問所に学んだ漢学者で、水野忠弘が朝日山藩に転封された際、藩の儒者として藩主に伴って近江を訪れ、廃藩後も教員として ...
-

-
世界平和を願い各国要人に富士の絵を贈った山元桜月
2023/9/29
山元桜月(1887-1985)は、滋賀県大津市白玉町(現在の大津市浜町)に生まれた。山元春挙は叔父にあたる。16歳の時に春挙の門に入り「春汀」の号を与えられた。明治40年に文展が創設されるとその第1回 ...
-

-
近江ゆかりの山元春挙の門人
2023/9/27
山元春挙は、京都市立美術工芸学校、京都市立絵画専門学校で教鞭をとって多くの教え子を育て、明治33年からは画塾・同攻会(のちに早苗会と改称)を結成して後進の指導にあたった。主な教え子としては、春挙門下四 ...
-

-
明治・大正期の京都画壇の重鎮として活躍した山元春挙
2024/12/13
旧膳所城下(滋賀県大津市)に生まれた山元春挙(1871-1933)は、小学校卒業後、大島一雄に漢詩文を学び、12歳の時に近江出身で四条派の野村文挙に師事して本格的に画をはじめた。その後、文挙が森寛斎に ...
-
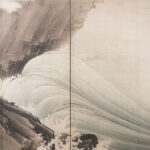
-
風景画を追究した湖東の自然画家・邨松雲外
2023/9/8
邨松雲外(1870-1938)は、滋賀県愛知郡小田苅村(現在の東近江市)に生まれた。13歳の時に神崎郡川並村の塚本家に奉公に出たが、生来画を描くことが好きで、20歳の時に退職し、京都に出て円山派の森寛 ...