-

-
青木繁・坂本繁二郎を指導した筑後洋画の先覚者・森三美
2024/12/20
福岡県久留米市とその周辺は、筑後洋画壇とよばれる独特の芸術風土を持ち、明治以来青木繁や坂本繁二郎ら多くの優れた洋画家を輩出してきた。そうした芸術風土や人脈形成にはさまざまな要因が考えられるが、京都で学 ...
-

-
官展で活躍した福岡県の近代日本画家
2024/12/11
官展で活躍した福岡県の近代日本画家としては、ます最初に吉村忠夫(1898-1952)が挙げられる。吉村は北九州市に生まれ、東京美術学校を首席で卒業、のちに松岡映丘に師事し、師と同様に歴史風俗画を得意と ...
-

-
新南画ともいえる独自の画風を開拓した冨田溪仙
2024/12/11
福岡県を代表する近代日本画家としては、福岡市生まれの冨田溪仙(1879-1936)が挙げられる。溪仙は、上田鉄耕に学んだのち、京都に出て四条派の都路華香に入門、25歳で華香門を独立した。明治45年、文 ...
-

-
近代大和絵の黎明期を担った川辺御楯
2021/7/8
筑後国山門郡柳川上町(現在の柳川市)に生まれた川辺御楯(1838-1905)は、守住貫魚、山名貫義、川崎千虎らと共に近代大和絵の黎明期を担った、明治初期を代表する大和絵歴史画家として知られている。しか ...
-

-
福岡南画壇の育ての親と称される中西耕石
2021/7/8
福岡県の近代南画の先駆者としては、福岡南画壇の生みの親とも育ての親とも称される中西耕石(1807-1884)が挙げられる。耕石は、遠賀川河口の貿易港として江戸時代に栄えた芦屋に生まれ、京都で松村景文に ...
-

-
江戸後期の筑前四大画家
2021/7/6
江戸後期、狩野派の御用絵師たちが粉本主義に陥り、精彩を失っていくなか、筑前画壇では町絵師たちが独自の画業を展開していた。なかでも元秋月藩御用絵師でのちに大宰府で町絵師として活躍した斎藤秋圃、藩から召し ...
-
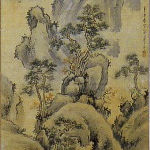
-
大宰府画壇を盛り上げた吉嗣家と萱島家
2021/7/8
天満宮の門前町として栄えた大宰府は、昔から文人墨客が往来し賑わいを見せていた。文政9年には秋月藩御用絵師を退いた斎藤秋圃が大宰府に移り住み、自由な町絵師として活躍した。秋圃の描いた絵馬は、大宰府、筑紫 ...
-

-
筑前秋月藩御用絵師・斎藤秋圃と門人
2021/7/6
筑前秋月藩の御用絵師・斎藤秋圃(1769-1861)は、京都に生まれ、円山応挙に学び、応挙没後は森狙仙に師事したと伝えられる。大坂時代の秋圃は、新町遊郭の風俗を題材とした「葵氏艶譜」の刊行などで知られ ...
-

-
筑後柳河藩御用絵師・梅沢晴峩と北島勝永
2021/7/6
柳河藩においては、江戸初期から中期にかけての文書や書画類が多く焼失しており、御用絵師の存在を確認できるのは江戸後期になってからである。それ以前の柳河藩には、福岡藩の尾形家や久留米藩の三谷家のように代々 ...
-
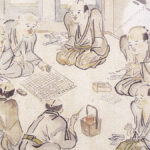
-
雲谷派が祖となった筑後久留米藩御用絵師・三谷家
2021/7/24
安芸国広島に生まれた雲谷派の三谷等哲(不明-1630)は、主家の断絶とともに浪人となり、子の等悦とともに筑後の久留米に移住した。久留米藩二代藩主・有馬忠頼は、等哲・等悦父子の人格技量を認め、等哲没後に ...
-

-
福岡藩御用絵師・衣笠家と上田家
2021/7/6
福岡藩御用絵師筆頭の尾形家が、藩主画像や城郭殿舎の内部絵付、席画や寺社の寄進画の制作などを主な仕事にしていたのに比べ、次席に位置する衣笠家が藩主画像や席画の御用にあたった形跡はほとんどなく、絵図の御用 ...
-

-
福岡藩御用絵師尾形家の絵師
2021/7/14
尾形家は、6代洞谷(1753-1817)の代になって、師家を鍛冶橋狩野家から駿河台狩野家に変更した。また、姓を公式に小方から尾形に改めたのも洞谷の代だった。7代の洞霄(1791-1863)は駿河台狩野 ...
-
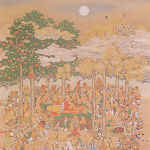
-
狩野探幽門下四天王と称された尾形家2代守義と狩野姓を許された3代守房
2021/7/24
福岡藩の御用絵師はすべて狩野派で、尾形家、衣笠家、上田家の3家が代々世襲で家督を継いだ。他にも、熊本氏、小森氏、佐伯氏、笠間氏など一代限りまたは随時に抱えられたと思われる絵師も少なくない。最も高禄だっ ...
-

-
筑前福岡藩御用絵師となった狩野宗家中橋家の狩野昌運
2021/7/6
狩野宗家中橋家で組織の確認と整備を図り、宗家の大番頭と称されていた狩野昌運(1637-1702)は、筑前福岡藩の第4代藩主・黒田綱政に招かれ、晩年の10年余りを福岡藩御用絵師として過ごした。絵師のなか ...
-

-
写実理論を作品と執筆の両面から確立しようとした前田寛治
2024/12/14
鳥取県中部の中北条村国坂の農家の二男として生まれた前田寛治(1896-1930)は、倉吉中学を卒業後、東京美術学校を卒業して倉吉中学に赴任したばかりの中井金三の勧めもあって画家を志し、上京して東京美術 ...
-

-
鳥取の近代的文化運動の中核となって活動した中井金三と砂丘社
2021/7/9
明治末期から大正にかけて、東京美術学校で学んだ新進気鋭の指導者たちが、鳥取中学、師範学校、倉吉中学に着任し、広く洋画が普及していった。さらに、大正末期から昭和初期になると、美術だけでなく芸術全般の活動 ...