-

-
孫億に学んだ宮廷画家・山口宗季(呉師虔)
2021/7/6
石嶺伝莫、上原真知に継いで、第二次派遣として1704年に福建省福州に留学したのが宮廷画家の山口宗季(1672-1743)である。福建省に滞在中は、中国伝統の写生画法を学び、4年間の留学を終えて帰国、そ ...
-

-
琉球絵師を指導した福建画壇の画家・孫億
2021/7/6
17世紀後半から18世紀にかけて、琉球王府は、貝摺奉行所の絵師を薩摩藩や中国の福建省福州に派遣し、現地の画家から直接指導を受けさせた。中国に絵画留学した初の琉球絵師は、石嶺伝莫(1658-1703)と ...
-
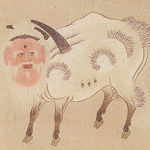
-
琉球絵師として最初に名を残した自了(城間清豊)
2021/7/6
琉球絵画は、13世紀に伝来した仏教文化に刺激を受けて発達したと考えられている。王国時代には、王府の行政機構に「貝摺奉行所」という部署があり、ここに絵師も所属して、漆器や着物の図案、室内装飾に携わってい ...
-

-
セザンヌを日本に初めて紹介した有島生馬と二科会の発足
2024/12/11
有島生馬(1882-1974)は、横浜市生まれだが、父親が薩摩川内市の出身で、鹿児島の画家との関わりは深い。文学者の兄・有島武郎、弟・里見弴とともに、有島三兄弟としても名高い。有島は東京外国語学校イタ ...
-
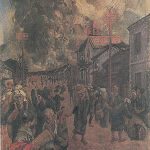
-
鹿児島洋画壇の黄金期をつくった山下兼秀と谷口午二
2021/7/6
鹿児島市に生まれた山下兼秀(1882-1939)は、東京美術学校では師の黒田清輝に可愛がられ、周囲からは白馬会研究所を継ぐものと思われていたが、ヨーロッパ留学を目前にしていたころ、母親が急逝したため、 ...
-

-
もうひとりの鹿児島洋画の先覚者・時任鵰熊
2021/7/6
鹿児島洋画壇の祖・大牟礼南島の2年後に東京美術学校の西洋画科を卒業したのが、もうひとりの鹿児島洋画の先覚者と称される時任鵰熊(1874-1932)である。時任は、鹿児島で教師をしていたが辞職して上京、 ...
-

-
鹿児島洋画壇の祖と称される大牟礼南島
2021/7/6
鹿児島出身の画家で、はじめて油彩画を描いたのが床次正精、はじめて正式に技術を学んだのが曽山幸彦、そしてはじめて本場西洋で学んだのが黒田清輝であり、ついで藤島武二、和田英作と日本近代洋画を代表する洋画家 ...
-

-
「大正の歌麿」と称された橋口五葉
2024/12/11
明治31年に東京美術学校に新設された西洋画科は、黒田清輝が初代教授をつとめ、藤島武二、和田英作も助教授として教鞭をとっていたため、鹿児島出身の画家たちで同校西洋画科に学んだものは多い。のちに浮世絵版画 ...
-
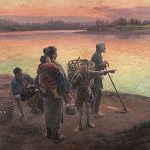
-
鹿児島近代洋画第三の巨匠・和田英作
2024/12/14
黒田清輝、藤島武二につぐ鹿児島近代洋画第三の先達である和田英作(1874-1959)は、明治29年に東京美術学校に西洋画科が開設された際、藤島と同時に助教授に招かれている。しかし、自身が正規の学校を出 ...
-
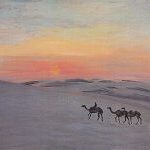
-
日本近代洋画の牽引者・藤島武二
2024/12/14
明治31年、東京美術学校に西洋画科が新設され、黒田清輝(1866-1924)が初代教授に就任した際、黒田が助教授に推薦したのは、三重県の尋常中学で教師をしていた藤島武二(1867-1943)だった。藤 ...
-

-
鹿児島が生んだ日本近代洋画の父・黒田清輝
2024/12/11
明治26年、10年間のフランス留学を終えて黒田清輝(1866-1924)が帰国した。黒田の留学は、はじめ法律を学ぶためのものだったが、外光派の画家ラファエル・コランとの出会いによって画業に専念すること ...
-

-
鹿児島の画家で初めて正式に洋画を学んだ曽山幸彦
2021/7/6
鹿児島の画家で最も早く油彩画を描いた床次正精は、本格的な画法の修得のためイタリア留学を希望していたがついに叶わず、独学で洋画技法を学ぶにとどまった。ついで登場した曽山幸彦(1859-1892)は、工部 ...
-

-
鹿児島の画家で初めて油彩画を描いた床次正精
2021/7/6
日本近代洋画の黎明期、鹿児島からは黒田清輝、藤島武二ら多くの著名洋画家が出て美術史に名を残したが、黒田や藤島よりも早く、鹿児島の画家で初めて油彩画を描いたのは、司法省に入り、検事や判事をつとめていた床 ...
-

-
奄美大島に没した田中一村の話
2021/7/6
昭和59年(1984)、田中一村(1908-1977)が奄美大島で没して7年後、NHK教育テレビ「日曜美術館」で「黒潮の画譜~異端の画家・田中一村~」と題して一村の画業が紹介され、大きな反響を呼んだ。 ...
-

-
小松甲川ら鹿児島の初期日本画家
2021/7/6
薩摩藩御用絵師・佐多椿斎の子として鹿児島に生まれた小松甲川(1857-1938)は、上京して明治政府の印刷局石版科長をしていた郷土の絵師・柳田龍雪に師事、同時期に橋本雅邦にも学び、近代的な日本画の影響 ...
-

-
明治期に活躍した鹿児島の狩野派・江口暁帆
2021/7/6
幕末の鹿児島に生まれ、少年期に狩野派を学んだ江口暁帆(1839-1921)もまた、時代の大きな変遷期にあって、伝統と変革の間で揺れ動きながら新しい表現を模索した画家のひとりである。暁帆の作品には、伝統 ...