-

-
大正期の大阪での女性画家ブームのなか、島成園らとともに多彩な活動をした岡本更園
2024/12/11
岡本更園(1895-不明)は、摂津国有馬郡名塩村(現在の兵庫県西宮市)に生まれた。姉が嫁いだ日本画家の岡本大更(参考)の家に寄寓し、16歳の時から義兄の更彩画塾で学んだ。大正3年に19歳で第8回文展に ...
-

-
妖艶で官能的な女性表現が注目された岡本神草
2024/12/11
岡本神草(1894-1933)は、兵庫県神戸市に生まれた。大正4年、京都市立美術工芸学校を卒業後、京都市立絵画専門学校(現在の京都市立芸術大学)に進学した。大正7年同校を卒業し、卒業制作の「口紅」(掲 ...
-

-
端正な女性像に回帰して帝展で注目された谷角日沙春
2024/12/11
谷角日沙春(1893-1971)は、兵庫県美方郡新温泉町諸寄に生まれた。小学校を出て父の回漕業を手伝い、その後も漁師や水手などをしながら画を独学した。20歳の時に偶然浜坂に滞在していた立脇泰山に師事し ...
-

-
簡素な画面構成で存在感ある女性像を描いた寺島紫明
2024/12/11
寺島紫明(1892-1975)は、兵庫県明石市に生まれた。少年時代から文学に傾倒し、寺島玉簾のペンネームで「少年倶楽部」などの雑誌に応募し入選した。17歳で文学を志して上京したと思われるが、その後画家 ...
-

-
飄逸にしてモダンな画風で異彩を放った水越松南
2024/3/8
水越松南(1888-1985)は、姫路藩の漢学者の子として神戸に生まれ、第一神戸中学校を中退して京都に出て谷口 香嶠(参考)に師事し、その後京都市立美術工芸学校図案科に入学した。明治43年の同校卒業後 ...
-

-
潜水艦に乗り込み魚類の生態を観察した大野麦風
2024/3/6
大野麦風(1888-1976)は、東京に生まれ、洋画家の長原孝太郎に学んだ。明治42年第3回文展で初入選し、以後、白馬会、太平洋画会、光風会など洋画団体の展覧会に出品した。大正2年には小石川の元白馬会 ...
-

-
国画創作協会などの新しい動きに共鳴し日本画と西洋画を融合した実験的技法を模索した山下摩起
2024/3/4
山下摩起(1890-1973)は、兵庫県有馬町の旅館「下大坊」の長男に生まれた。京都市立美術工芸学校、京都市立絵画専門学校に学び、在学中に文展初入選を果たした。卒業後は西宮に移り、文展、帝展に出品する ...
-

-
文展を離れ国画創作協会を結成した村上華岳
2024/12/14
村上華岳(1888-1939)は、大阪市に生まれ、16歳の時に叔母の婚家である村上家の養子となり神戸花隈で育った。明治40年、京都市立美術工芸学校を卒業して専科に進み、翌年第2回文展で初入選を果たした ...
-

-
兵庫県画壇の重鎮として活躍した立脇泰山
2024/2/28
立脇泰山(1886-1970)は、兵庫県美方郡浜坂町(現在の新温泉町)に生まれた。幼いころから画を好み、京都に出て京都市美術工芸学校(現在の京都市立芸術大学)で学んだ。掲載の「黄昏」は卒業制作。その後 ...
-

-
栖鳳門下で美人画に独自の境地を開いた三木翠山
2024/12/14
三木翠山(1887-1957)は、兵庫県加東郡社町(現在の加東市)に生まれた。幼いころから画を好み、同じ社町の三木南石に画の手ほどきを受け、望まれて三木家の養子となった。その後京都に出て竹内栖鳳(参考 ...
-
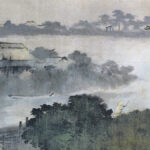
-
兵庫県日本画壇で指導者的な立場で活躍した森月城
2024/2/23
森月城(1888-1961)は、兵庫県加東郡社町(現在の加東市)に生まれた。幼いころから母方の祖父・三木南石に画の手ほどきを受け、13歳の時に京都に出て竹内栖鳳に師事した。20歳の時に第12回新古美術 ...
-

-
戦後は官展を離れ故郷の淡路島で活動した不動立山
2024/2/21
不動立山(1886-1975)は、兵庫県三原郡西淡町(現在の南あわじ市)に生まれた。京都市立絵画専門学校(現在の京都市立芸術大学)で学び、その後西山翠嶂(参考)の画塾「青甲社」に入った。大正元年の第6 ...
-

-
国内外を旅し戦争画でも名作を残した小早川秋声
2024/2/19
小早川秋声(1885-1974)は、鳥取県日野郡日野町にある光徳寺の長男として生まれ、母親の里である神戸の九鬼子爵邸内で育ち、9歳で東本願寺の衆徒として僧籍に入った。幼いころから画を好み、中学在学中か ...
-

-
欧州放浪を含めた15年間の沈黙ののち華々しい画壇への再登場を果たすが46歳で急逝した青山熊治
2024/2/16
青山熊治(1886-1932)は、兵庫県朝来郡生野町(現在の朝来市)に生まれた。同じ生野出身の白滝幾之助、和田三造とともに「生野の三巨匠」と称されており、3人はいずれも東京美術学校西洋画科で学び、白馬 ...
-

-
画壇から離れ西宮で静かな作画活動を行なった新井完
2024/2/14
新井完(1885-1964)は、兵庫県姫路市に生まれた。父と早く死別したこともあって姫路中学を中退して叔父を頼って上京し、日本中学に転入した。明治38年東京美術学校に入学し、同校卒業の翌年に文展初入選 ...
-

-
油彩画「南風」で一躍名を馳せ、その後は日本画、色彩研究、舞台美術など幅広い分野でマルチに活躍した和田三造
2024/12/14
和田三造(1883-1967)は、兵庫県朝来郡生野町(現在の朝来市)に生まれた。15歳の時に家族とともに福岡市に移ったが、翌年画家を志して福岡を出奔して上京、黒田清輝邸の住み込み書生となり、白馬会洋画 ...