-
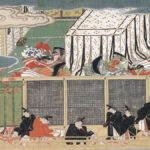
-
土佐派と唯一拮抗する活動を展開した粟田口隆光
2025/12/3
大阪・誉田八幡宮に伝わる「誉田宗廟縁起絵巻」は、永享5年(1433)、6代将軍・足利義教が奉納した絵巻で、全3巻に応神天皇の崩御・葬送と陵墓建設、欽明天皇の勅定により山陵のかたわらに宝殿を建立し八幡大 ...
-

-
絵師として初めて土佐を称した土佐行広
2025/12/1
土佐行広(不明-不明)は、藤原光重の子で、藤原行秀とは兄弟だったと推測されている。兄と目される行秀が工房「春日絵所」を継承し、絵所預をつとめたのに対し、行広は主として将軍家周辺での画事を行なった。初期 ...
-

-
春日絵所の基盤を固めた藤原行秀
2025/11/28
藤原行秀(不明-不明)は、藤原光重の子で、絵師として初めて土佐を称した土佐行広の兄と推定されている。六角寂済らとともに、応永21年の清凉寺本「融通念仏縁起絵巻」の制作に参加しており、当時は現職の絵所預 ...
-

-
行光の工房を継承した藤原光重
2025/11/26
土佐派の実質的な祖とされる藤原行光の次世代にあたるのが、藤原光益(六角寂済)と藤原光重(不明-不明)で、いずれも行光の子と推定されている。先に絵所預に就任した光益が兄と思われるが、光重が行光の工房を継 ...
-

-
清凉寺「融通念仏縁起絵巻」制作に加わった六角寂済
2025/11/24
「融通念仏縁起絵巻」は、融通念仏宗を開いた良忍上人の伝記と念仏の功徳を描いた上下2巻の絵巻で、鎌倉末期に原本が成立し、近世に至るまで大量の転写本や版本が制作された。なかでも、応永21年に成立した「清凉 ...
-

-
土佐派の実質的な祖とされる藤原行光
2025/11/21
藤原隆章・隆昌父子とほぼ同時期、土佐派の実質的な祖となる藤原行光(不明-不明)は、足利将軍家および北朝の周辺でやまと絵制作を行ない、絵所預となった。その後、この絵所預の職は行光の子孫たちによって継承さ ...
-

-
京都西本願寺「慕帰絵」を描いた藤原隆章・隆昌父子
2025/11/19
京都・西本願寺に伝わる「慕帰絵」は、親鸞の曾孫で本願寺三世となった覚如の生涯を綴った高僧伝絵巻で、門弟の乗専を発起人に、覚如の没後まもなく制作された。覚如の生誕から宗教者として成長をとげていく過程を主 ...
-

-
三代にわたって同じ号を用いた山田道安
2025/11/17
山田道安は、洞が峠で聞こえた筒井順慶の一族で、画や彫刻にすぐれたという。道安の号は三代にわたって用いたとされるが、作品のうえからは初代と二代の二人らしく、いずれも鐘馗の絵を得意とし、ほかに山水、花鳥、 ...
-

-
周文の画風を学んだとみられる武人画家・土岐富景
2025/11/14
戦国時代の美濃では、城主・土岐氏の一族から数人の武人画家が出ている。土岐富景(不明-不明)もその一人だが、土岐氏の一族であるということ以外の伝記は不明である。美濃守を称したことは落款から知られているが ...
-

-
越前曾我派が代々名乗ったとみられる「曾我蛇足」
2025/11/12
京都・真珠庵の襖絵で知られる曾我蛇足は、越前曾我派の祖で周文に画を学んだ墨溪の別号として伝わっていたが、制作年代などから襖絵を描いたのは曾我派2代の宗丈という説が有力となり、曾我蛇足という画名も個人の ...
-

-
相阿弥に学んだと伝わる単庵智伝
2025/11/10
単庵智伝(不明-不明)については、長谷川等伯著『等伯画説』の記述が唯一の手掛かりで、それによると、尼崎の器物の下絵付師の出身で、相阿弥に望まれて弟子になったとされ、相阿弥のもとへ修行に出る時、絵の手本 ...
-

-
東山文化の中心的存在として活躍した相阿弥
2025/11/7
相阿弥(不明-1525)は、父・芸阿弥の跡を継ぎ、八代将軍・足利義政に同朋衆として仕え、歴代将軍の蒐集品を管理・鑑定する唐物奉行をつとめた。一方で、画事、連歌、作庭、生花、香道など諸芸に才能を発揮する ...
-

-
能阿弥の跡を継いで足利義政に仕えた芸阿弥
2025/11/5
芸阿弥(1431-1485)は、父・能阿弥の跡を継いで足利義政に仕え、連歌、表装、座敷飾、画事といった幅広い分野で幕府の御用をつとめた。画事においては、将軍家が所蔵する中国・宋時代の画院画家・夏珪の山 ...
-

-
将軍家所蔵の美術品を管理し阿弥派を形成した能阿弥
2025/11/3
日本における初期の水墨画は、黙庵、可翁、良全、鉄舟、梵芳、愚渓らが中国の絵画様式をもとに日本的なものを模索し、15世紀に入ると京都五山の禅僧たちがその中心的役割を果たした。東福寺では明兆、および明兆一 ...
-

-
雪舟を通して牧谿を学んだと思われる周耕
2025/10/31
13世紀後半の中国の画僧・牧谿が描くテナガザルは「牧谿猿」と呼ばれ、日本では室町時代から桃山時代にかけて流行した。数多くの画人が牧谿を模して猿を描いており、雪舟等楊、秋月等観、式部輝忠、土岐洞文、雪村 ...
-
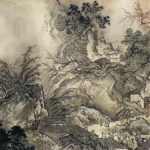
-
京都を離れ中国や日本各地を巡った雪舟
2025/10/29
雪舟等楊(1420-1502)は、備中(現在の岡山県)に生まれ、少年時代は故郷に近い井山の宝福寺に入って小僧になったと伝わっている。涙でネズミを描いたという有名な伝説も、この寺での逸話となっている。そ ...